レゾナンスのバーチャルオフィスお役立ちコラムでは、バーチャルオフィス(住所貸し)に関する情報はもちろん起業や副業・ビジネスに役立つ情報をお届けします。既に会社をお持ちの方、フリーランス、個人事業主の方は情報収集に是非ご活用ください。
 バーチャルオフィス
バーチャルオフィス バーチャルオフィスからリアルオフィスへ移行するときのタイミングは?|準備のステップや注意点を解説
 バーチャルオフィス
バーチャルオフィス バーチャルオフィスの料金・契約期間に関する疑問とトラブル事例【予防チェックリストも紹介】
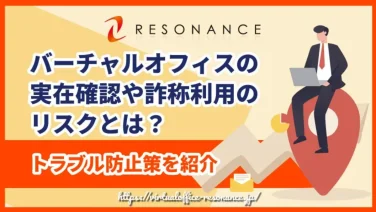 バーチャルオフィス
バーチャルオフィス バーチャルオフィスの実在確認や詐称利用のリスクとは?トラブル防止策を紹介
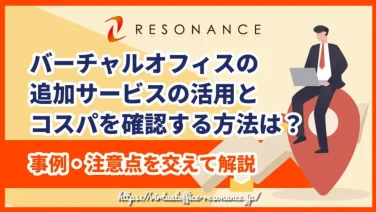 バーチャルオフィス
バーチャルオフィス バーチャルオフィスの追加サービスの活用とコスパを確認する方法は?事例・注意点を交えて解説
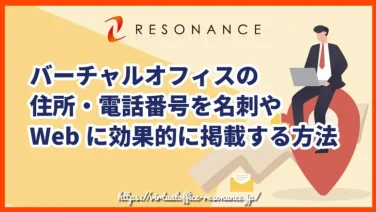 バーチャルオフィス
バーチャルオフィス バーチャルオフィスの住所・電話番号を名刺やWebに効果的に掲載する方法
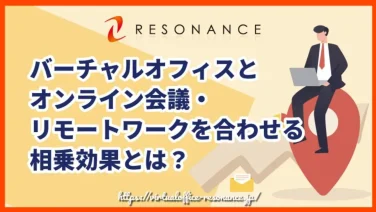 バーチャルオフィス
バーチャルオフィス バーチャルオフィスとオンライン会議・リモートワークを合わせる相乗効果とは?
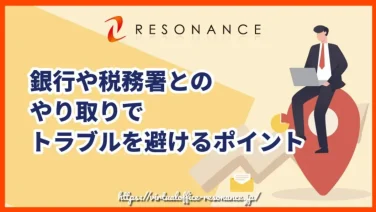 バーチャルオフィス
バーチャルオフィス 銀行や税務署とのやり取りでトラブルを避けるポイント【バーチャルオフィス】
 バーチャルオフィス
バーチャルオフィス バーチャルオフィスの郵便物管理や電話代行で業務効率アップ!活用事例を紹介
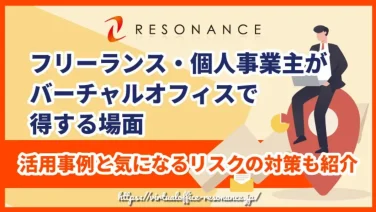 バーチャルオフィス
バーチャルオフィス フリーランス・個人事業主がバーチャルオフィスで得する場面|活用事例と気になるリスクの対策も紹介
 バーチャルオフィス
バーチャルオフィス 











