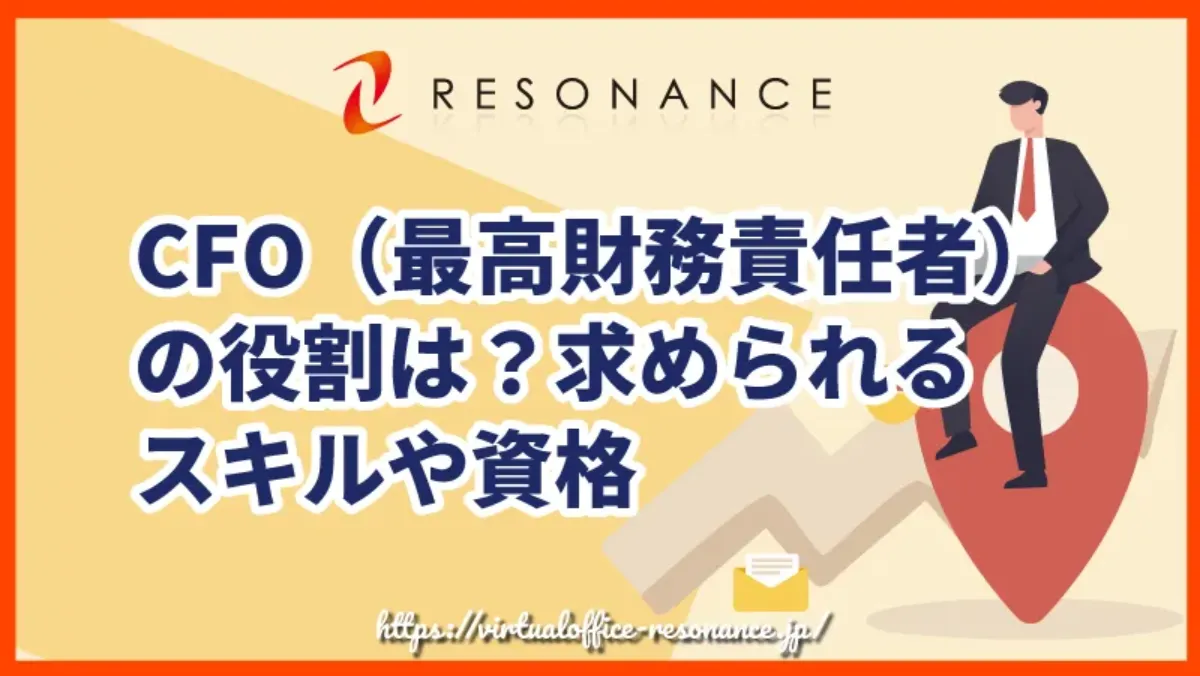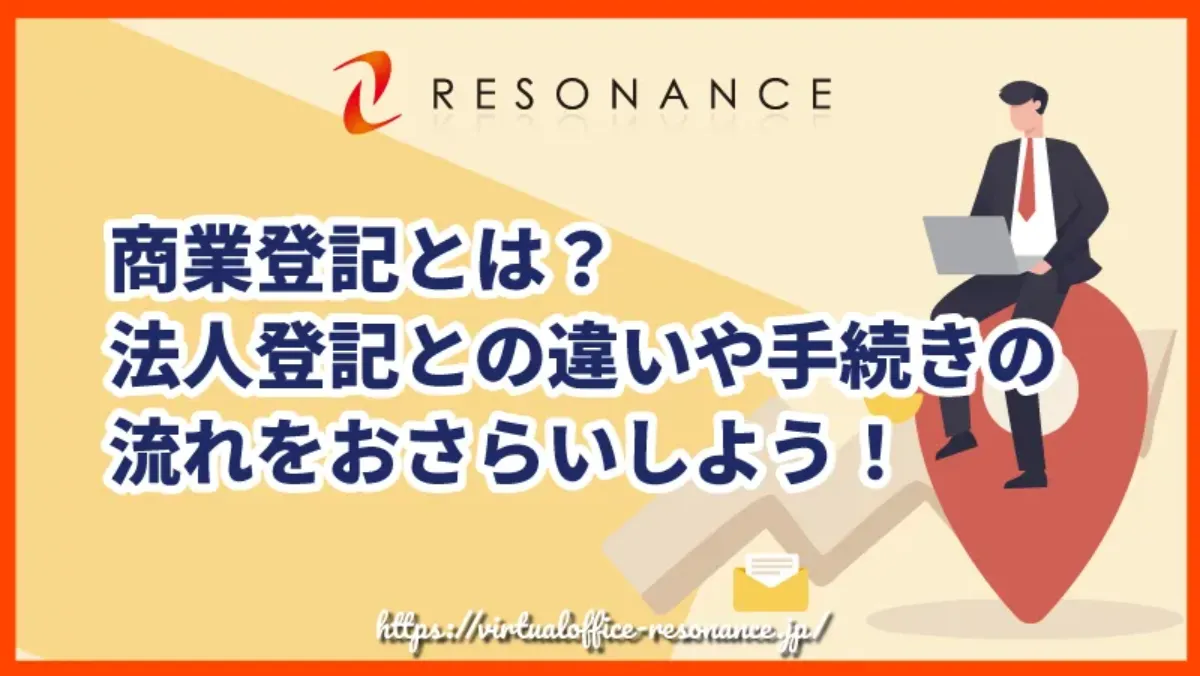グローバル化に伴い日本の経営環境はめまぐるしく変化するなかで、高い透明性を求められる国際会計基準や欧米機関投資家にむけた株主主体の経営指標などの導入により、企業が生き残るためには財務部門の強化が不可欠となってきました。
そんななかで、財務部門と企業経営において重要なポジションに位置するのが、「CFO(最高財務責任者)」。
欧米においては、CFOは単なる企業財務の専門家としてだけでなく財務を企業戦略に取り込む経営者として、CEO(最高経営責任者)と並び、企業経営にける重要なポジションとして、そのステータスが確立されています。
そこで、財務や経理からのキャリアアップの選択肢の1つとして、CFOを目指している方に向けて、CFOについて役割や職務内容を解説し、必要なスキルや資格についてご紹介します。
CFO(Chief Financial Officer)とは
CFOとは「Chief Financial Officer(チーフ・ファイナンシャル・オフィサー)」の頭文字をとった略語で、日本では「最高財務責任者」と訳されています。
財務部長などの役職がこれに近く、企業の財務戦略の立案から執行までを執り行う財務部の最高責任者にあたります。
財務部はもともと、健全で収益性の高い企業への成長に向けて、資金繰りやお金の管理などを行う部門ですが、CFOは、その最高責任者としてだけでなく、財務戦略によって企業活動をマネジメントしていくための企業経営にも関わります。
欧米においては、CFOは必ずしも財務部門からのキャリアアップだけでなく、営業部門や管理部門からキャリアアップした人材も活躍しています。
CFOの役割
CFOは、財務戦略の立案や執行だけではなく、CEOとともに経営陣のひとりとして、企業発展に向けた大きな役割を担います。
財務諸表を作成・開示したり、銀行からの資金調達をしたりするだけにとどまらず、ライバル企業との競合に打ち勝つための戦略と立案するために、企業内の各事業部門と協議を重ねて利益率の向上を図ったり予算管理を行います。
企業の流動資産のほか工場設備や研究開発費などに対して、どのように投資したら将来のキャッシュフローを最大限に引き上げられるか、などを含めたオペレーションについて、数値化して冷静に判断し導くという重要な役割をも担うのがCFOなのです。
CFOが生まれたきっかけとは?
CFOが生まれたきっかけは、バブル崩壊による金融機関の破綻です。
これにより金融機関からの資金調達が困難となった企業は、投資家などからの資金調達を行うために、投資家に向けた財務戦略の開示説明をする必要性が生まれました。
それまでの金融機関に対するのとは異なり、投資家に対しては、自社マーケットにおける成長性や優位性などについて、より納得のいくものにする必要性が生まれました。中間管理職の位置づけである財務部長では、経営知識や経営者的目線などが不足していたことから、CFOという職位が生まれました。
CFOの具体的な職務内容

資金調達
企業が経営活動を行うための資金調達は、財務部門の基本です。
資金調達には、次の2種類があります。
- 融資
- 出資
運営資金が少なければ、金融機関などからの借り入れを行って資金調達を行う必要があります。融資を受けるために「財務諸表」を整理し、返済計画などを提出します。
ベンチャーキャピタルや投資家に対して、新規株式を発行し出資を受けることで資金調達を行います。ベンチャーキャピタルや投資家の候補リストを作り、発行する株式の数・種類についての交渉を行います。
財務戦略の立案
社内の事業部門ごとに必要となる資金の振り分けや、コストカットへの取り組みなどについて、自社の事業計画やKGI(重要目標達成指標)、KPI(重要業績評価指標)を考慮しながら、実現性の高い財務戦略を立案します。
内部統制
内部統制とは、企業目標を達成するための企業内での仕組みやルールの構築を行うことです。部門間の連携や調整を行いながら、業務の効率性や法令遵守、資産保全などについて、内部統制によって整備を行います。
特に、上場を目指す際や事業を拡大する際は、業務の増加や分担に関して問題が起こりやすいので、部門間の連携を高めるマネジメントの必要性が高まります。
監査法人や証券会社、ステークホルダーとの調整
CFOは、上場にむけた監査法人や証券会社の選定・渉外も行います。
上場を成功させるためには、上場前後に必要となる監査に向けて、慎重に監査法人を選定することが重要となります。証券会社についても、自社ビジネスへの理解度を見ながら選定します。
また、経理部長主導でまとめた決算数値などを使って、社外のステークホルダー(利害関係者)と、企業の方向性や戦略などもって利害調整や、投資家への説明なども行います。
CFOに求められるスキル
CFOはCEOとならぶ重要なポジションにあたるので、さまざまなスキルが求められます。
企業会計・企業財務に関する知識
CFOは、まずは企業会計や企業財務に関して広く深い専門的知識が必要となります。
これらの知識は、優れた財務戦略を立案するためには必須で、上場企業での会計・財務・IR部門での実務経験やIPO(新規上場株式)経験を有するレベルが求められます。
具体的に役立つ職務知識としては、「資金調達」、「資金運用」、「ROEマネジメント」、「投資採択基準」、「配当方針」、「資本コスト管理」などです。
経営に関する知識と経営陣としての意識
CFOは、CEOのビジネスパートナーとして財務戦略を中心に他社動向を分析しながら自社の経営課題を把握し、経営判断への意見を述べる役割もあるため、経営に関する深い知識が求められます。
また、CEOに次ぐリーダーシップも求められ、常に経営に参加しているという経営陣としての高い自覚も求められます。
法令に関する知識
CFOには、さまざまな法令に関する知識も求められます。
金融商品取引法や、銀行法、保険業法などの法令知識のほか、管理部門を統括する立ち位置から、労務や個人情報、そしてコンプライアンス(法令遵守)についての知識も必須となります。
コミュニケーションスキル
CFOには、社内のさまざまな部門との連携、そしてCEOへ経営に関する意見を述べる機会もあり、高いコミュニケーションスキルが求められます。
さらに、資金調達のために投資家やステークホルダーへの説得や折衝を行うという重要な職務も担うため、論理的かつ説得力・安心感のある高い交渉力も必要となります。
さらに、海外のクライアントとの外国語を使ったコミュニケーション力も必要とされるでしょう。
CFOになるために必要な資格

CFOは、「取締役」や「部長」のように企業における立場の名称なので、必須となる資格は特にありません。
しかし、取得することでCFOになるのに役立つ資格はたくさん存在します。それらの資格を取得することで、CFOへの転職に優位になったり、権威性を高める肩書としても役立ったりするでしょう。
CFOを目指す上で有利となる資格としては、「一般社団法人日本CFO協会」が運営・管理を行う「プロフェッショナルCFO資格」が挙げられます。
日本CFO協会では、ファイナンス分野への従事経験のないビジネスマンでも、CFOあるいはCEOとして企業で活躍できるよう、企業財務の考え方や財務戦略の手法などを身につけるための教育体系となっています。
プロフェッショナルCFO資格では、コーポレートファイナンスの基礎をはじめ、経営計画の実施に至るまで、CFOとして必要な知識と技術を身に着けることができます。
またその他にも、日本CFO協会では「FP&A(経営企画スキル検定)」、「FASS検定(経理・財務スキル検定)」など、CFOの知識として役立つ検定試験を執り行っています。
- 公認会計士
- MBA(経営学修士)
- FASS検定
- 日商簿記検定試験
CFOは、CEOのビジネスパートナーとして企業経営に深く関わる重要な職位です。
さまざまなスキルが求められますが、企業における功績も大きく、非常にやり甲斐のあるポジションです。
将来のステップアップの目標に定め、トライしてみてはいかがでしょうか。