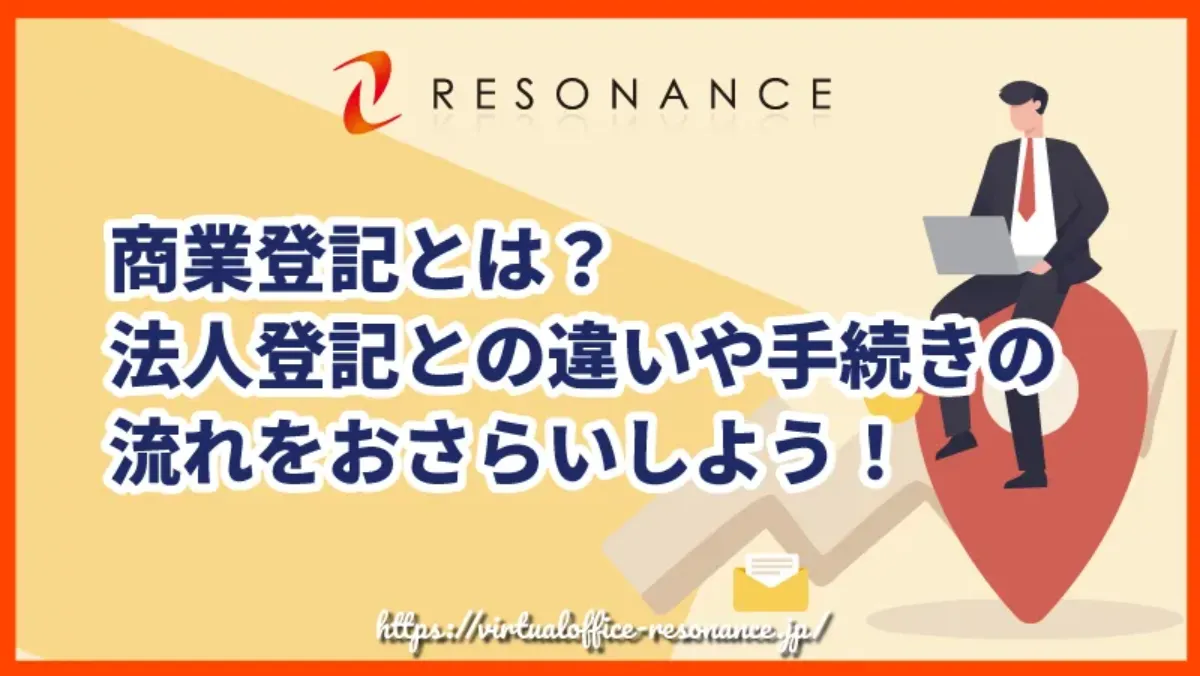昨今では、会社からの独立や副業で「個人事業主」になられる方が増えています。個人事業主になるには、どのような手順で手続きをすればよいのでしょうか?
ここでは個人事業主のメリット・デメリットをおさらいするとともに、開業届の作成から提出までの手順、開業の前後にやっておきたいことをまとめてご紹介します。
個人事業主になるには?メリット・デメリットをおさらい
個人事業主とは「個人で事業(反復・継続・独立したビジネス)を行う者」を指します。
個人事業主になる条件としては、所轄税務署へ「開業届」を提出するだけです。
開業届の提出は無料でできるため、副業やスモールビジネス等で「手軽に起業したい」という方でも気軽に個人事業主となれます。
個人事業主になるメリット
個人事業主は、個人の実力や仕事の量によって収入を増やすことができます。これは、会社からの評価により給与の額が決まる会社員と比べると大きな違いです。
また会社のように定年がなく、何歳になっても働けるのは個人事業主ならではの魅力だといえます。
そのほか、開業して個人事業主になると「青色申告」ができる点もメリットです。
青色申告をするには承認申請書の提出が必要ですが、確定申告時に「青色申告特別控除」として65万円を差し引いて申告できます。
また青色申告の場合、事業で生まれた赤字を3年繰り越すこともできます。
開業せず「白色申告」として確定申告をするのに比べると、節税効果は高くなるでしょう。
個人事業主になるデメリット
個人事業主を他の働き方と比べると、デメリットもあります。
まず個人事業主として65万円の青色申告特別控除を受けるには、複式簿記による帳簿付けが必須となります。
これにより、帳簿付けがやや煩雑である点はデメリットだといえるでしょう。
また会社員と比べると、個人事業主の社会的信用はどうしても低くなります。
さらに、仕事を獲得するには自身で営業・販促・宣伝を行わなくてはならず、直接的な業務以外の作業が発生する点も知っておきましょう。
個人事業主になるには「開業届」を提出する!その方法は?
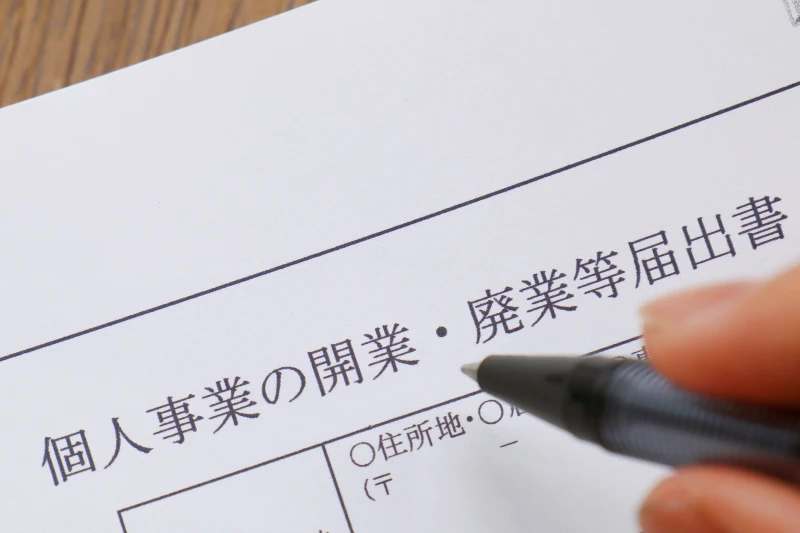
個人事業主について理解が深まったところで、知っておきたいのが「開業届の提出方法」です。
開業届はどこで入手できる?
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)とは「新たに事業を開始したとき、及び事務所や事業所を新設・増設・移転したとき」に提出する書類です。
個人事業主になるには、税務署へ開業届を提出する必要があります。
開業届は各地の税務署で入手できるほか、国税庁のHPで書式をダウンロードすることも可能です。
なお提出方法は税務署の窓口へ直接提出する方法だけではなく、郵送やe-Taxでの電子申請も可能です。
e-Taxを利用するには利用者識別番号の取得などの事前手続きが必要になるため、確認しておきましょう。
参考:ご利用の流れ | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
開業届の作成方法は?
開業届を入手したら、必要事項を記入しましょう。
- 納税地を管轄する税務署名
- 書類の提出日
- 納税地(住所地か居所地、事業所から選択可)
- 電話番号
- 開業した場所の所在地(自宅やオフィスなど)
- 氏名
- 生年月日
- マイナンバー(個人番号)
- 職業
- 屋号(任意)
- 届け出の区分(開業/廃業のうち開業を選択)
- 所得の種類
- 開業日
- 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無(同時に青色申告の申請をする場合は「有」へチェックを入れる)
- 具体的な事業内容
これらの内容を「開業届」「開業届(控え)」へ記入したら、税務署へ提出をしましょう。
提出時には以下の書類等を揃える必要があります。
①開業届
②開業届の控え(①のコピーでも可)
③マイナンバー確認書類、本人確認書類
④返信用切手を貼った返信用封筒(※郵送時のみ)
⑤青色申告承認申請書(青色申告を利用したい人)
③に関してはマイナンバーカードがあれば1つの提示(または写しの送付)のみで済みます。
また、青色申告をしたい場合は⑤の青色申告承認申請書もまとめて提出しましょう。
書式は以下からダウンロードできます。
個人事業主になるには他にも書類の提出が必要になるケースも
個人事業主になるには開業届の提出が最低条件となります。青色申告をする場合は、合わせて青色申告承認申請書の提出も必要です。
そのほか、場合によっては次のような書類の提出が必要になることもあります。
・配偶者や親族に支払った給与を経費計上したい場合
→「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」の提出が必要。
(参考:[手続名]青色事業専従者給与に関する届出手続|国税庁)
・初めて従業員(青色事業専従者を含む)を雇って給与を支払う場合
→「給与支払事務所等の開設届出書」の提出が必要。
(参考:[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出|国税庁)
・従業員を1人以上雇った場合
→雇用保険、労災保険の加入手続きが必要。
(雇用保険は管轄のハローワークへ、労災保険は都道府県労働局や労働基準監督署、ハローワークへ申請)
・特定の業種(工業や教育・医療などの法定16種)で従業員を5人以上雇った場合
→健康保険、厚生年金保険への加入が必要。
・従業員10人未満で、かつ源泉徴収税の納付を半年ごとにしたい場合
→「源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書」の提出が必要。
(参考:[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請|国税庁)
このように家族等の青色事業専従者へ給与を支払ったり、従業員を雇ったりする場合には、手続きが必要になる場合が多いと考えてよいでしょう。
開業後に複数人でビジネスを始める際には、必ず必要な手続きについて確認しておきましょう。
個人事業主になる前にやっておきたいことは?
個人事業主になるには、開業届の提出など簡単な手続きのみでOKです。
ただ、これから独立して開業するのであれば、会社にいるうちにローンやクレジットカードの申し込みを済ませておくとよいでしょう。
会社を辞めて独立する場合は、しばらくの間ローン申し込みやクレジットカード作成で不利になる可能性があります。個人事業主は会社員に比べて社会的信用が低く、審査で不利になることが多いからです。
特に住宅ローンの審査では「直近3期分の確定申告書」を求められるケースが多く、金融機関によっては独立後4年程度経たないと審査申し込みすらできない……というケースもあります。
ローン契約やクレジットカードの作成をしたい場合は、できる限り会社に在籍している間に申し込んでおきましょう。
個人事業主になったあとに必要な申請・手続きは?
会社を独立して個人事業主になるには、開業後に以下のような手続きも必要です。
- 国民健康保険への加入手続き
- 国民年金への加入手続き
それぞれを見てみましょう。
国民健康保険への加入手続き
会社を辞めて社会保険から脱退したあとは、速やかに国民健康保険へ加入しましょう。国民健康保険への加入手続きは、市区町村の役所で行います。
なお、国民健康保険に加入しない場合は、会社で加入していた健康保険を「任意継続」するか、業界特化型の国民健康保険組合などに加入する方法もあります。
後者の国民健康保険組合に関しては、「特定の団体・組合に所属している」「会員の推薦が必要」などの条件が提示されているケースも多いため、確認したうえで判断しましょう。
国民年金への加入手続き
会社を辞めて個人事業主になった場合は、年金も「国民年金」へと変更になります。
ただし国民年金の場合、会社員時代に加入していた厚生年金に比べると受取額は少なくなる点に要注意です。不足分を補うには、iDeCoや国民年金基金へ加入したり、自身で投資などをしながら資産形成をしたりする必要があることを理解しておきましょう。
個人事業主になるには簡単な手続きでOK!バーチャルオフィスも活用してみよう

個人事業主になるには、開業届の提出が最低限の条件となります。また確定申告で青色申告をする場合は、青色承認申請書の提出、電子申告をしたい場合はe-Taxの申し込みも併せて行いましょう。
最近では、ネットを使った在宅ビジネスで個人事業主になられる方も増えています。
ご自宅での開業を検討されている場合は、バーチャルオフィスを利用すると便利です。
バーチャルオフィスは、自宅の代わりにビジネスへ使えるレンタル住所のこと。
レゾナンスでは月額990円~(税込)からの格安で、バーチャルオフィスをご提供しております。
レゾナンスのバーチャルオフィスは一等地(東京都港区浜松町、港区青山、中央区銀座、中央区日本橋、渋谷区神南、渋谷区神宮前、渋谷区恵比寿、新宿区西新宿、千代田区神田、横浜市西区)からお好きな住所をお選びいただけるのが特徴。法人登記にも使用可能なため、「事業が好調になり法人化をしたい」という場合でも、乗り換える必要なくご利用いただけます。