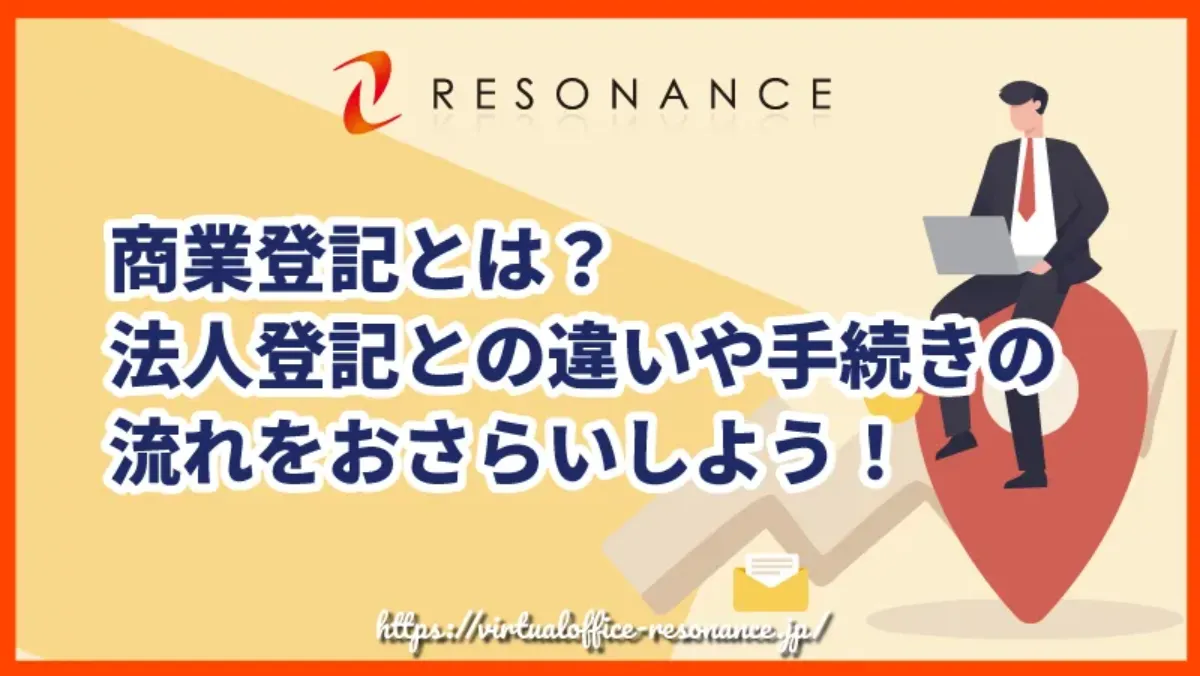2006年に新会社法が施行されて以降、株式会社であっても「資本金1円~、役員1名以上」での設立が可能となり、法人化のハードルがグッと低くなりました。これをお読みになっている個人事業主の中にも、法人化を視野に入れている方がいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、法人化のメリット・デメリットや、法人化を考えるタイミングをご紹介します。ぜひ参考にしてみて下さい。
法人化とは?法人成りするとどうなる?
「法人化」とは、個人事業主として活動していた人が法人登記をし、会社を設立することです。
「法人成り」とも呼ばれます。
個人事業主が法人化すると、個人ではなく「会社」として取引等を行うようになります。
その場合、以下のような変化が生じます。
- 「法人税」「法人事業税」「法人住民税」を納付することになる
- 個人事業主と違い、法人化により「役員報酬」という給与をもらうようになる
- ひとりでも社会保険に加入することになる
個人事業主としてビジネスを行っていたときと違い、法人格が与えられることで「法人専用の税」が課せられるようになります。
また個人事業主の場合は売上・報酬から得た利益が「所得」となっていましたが、法人化すると「役員報酬」という給与に変わる点も特徴です。
ちなみに、法人化すると健康保険や厚生年金、雇用保険、労災保険、介護保険などの「社会保険」に強制加入となります。ひとりで法人化した場合でも加入義務がありますので、覚えておきましょう。
法人化のメリット・デメリット
個人事業主が法人化した場合、さまざまなメリットが得られます。ただし、法人化にはデメリットもあるため、両方を把握しておくことが重要です。
法人化のメリット
法人化の主なメリットは、次の4つです。
- 信用度がアップし、取引や販売、融資で有利になる
- 税制の優遇が受けられ、売上が多いほど節税できる
- 法人形態によっては「有限責任」となり、経営悪化時のリスクが軽減される
- 事業承継がしやすくなる
信用度がアップし、取引や販売、融資で有利になる
法人化の大きなメリットとして、「信用度がアップする」という点が挙げられます。
大手企業などの中には、個人事業主との取引を避けるところも少なくありません。また融資を受ける場合も、会社に比べれば個人事業主は、信用性の観点でいうとやや不利です。
法人化して会社を設立することで、対外的な信用度は格段にアップします。そうなれば取引や販売、融資にも良い影響が表れやすくなりますし、さらなる業績アップ、ビジネスの展開も可能となるでしょう。
税制の優遇が受けられ、売上が多いほど節税できる
法人化すると、さまざまな税制優遇が受けられます。
- 役員報酬をもらう場合「給与所得控除」が受けられる(55~195万円)
- 役員の退任時にもらう「役員退職金」を損金計上できる
- 家族を従業員にした場合、給与を損金計上できる
- 法人税率の適用により、個人事業の所得税額よりも負担が少なくなるケースがある
- 最大2年間消費税の納税が免除される(資本金1,000万円以下の法人のみ)
- 赤字(繰越欠損金)がある場合、10年間控除できる
- 生命保険料を「経費」として計上できるようになる
特に「法人税率」については、所得900万円を超えた時点で所得税率(この所得帯では33%)よりも低くなります。法人税率は高くても23.20%までなので、売上が多くなるほど大きな節税効果が実感できるでしょう。(※)
そのほかの税制優遇についても、個人事業と比べると手厚いといえるでしょう。
※法人税率は15~23.20%で、資本金額や所得により異なります。
法人形態によっては「有限責任」となり、経営悪化時のリスクが軽減される
株式会社や合同会社では、出資した人が「有限責任」を負います。
責任とは「会社が負債を背負ったり、倒産したりした場合にどの範囲まで責任を問われるか」という意味で、有限責任は「出資額の範囲のみ責任を負う」ということになります。
たとえば株式会社なら、経営破綻を起こして倒産しても、購入した株式分の金額だけ責任を負います。会社のマイナス分を、自分の私財から補てんしなくてもよいのです。
事業承継がしやすくなる
個人事業の場合は資産すべてを相続しなくてはならないため、手続きが複雑です。
一方、株式会社の場合、会社の所有権は「株を持っている株主」にあります。
この場合、会社の所有権を譲りたい(事業承継)ときは株式を引き継ぐだけで承継ができます。
法人化のデメリット
法人化にはデメリットもあります。以下の4点を把握しておき、法人化の判断材料にしましょう。
- 法人設立費用や資本金などのお金がかかる
- 社会保険料の負担が増える
- 赤字でも住民税の負担が生じる
- 税務処理などの事務作業が煩雑になる
法人設立費用や資本金などのお金が必要
株式会社の場合は法人化に約25万円、合同会社の場合は約10万円の費用がかかります。
定款を電子定款で作成すれば印紙代(40,000円)が0円になりますが、それでも株式会社なら法人化に21万円以上、合同会社なら7万円以上がかかる計算になります。
さらに、法人用の印鑑を作るお金や定款作成ソフトなど、提出方法によって別途お金がかかる場合もあるでしょう。
| かかる費用 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 定款の認証手数料 | 50,000円 | なし |
| 印紙代 | 40,000円 (電子定款の場合は0円) |
40,000円 (電子定款の場合は0円) |
| 定款の謄本 | 約2,000円 | 約2,000円 |
| 登録免許税 | 150,000円 (資本金額により高くなる場合あり) |
60,000円 (資本金額により高くなる場合あり) |
| 会社の印鑑作成代 | 10,000円~20,000円 | 10,000円~20,000円 |
| 印鑑証明書代 | 1,000~2,000円 | なし |
| 電子定款システムを利用する場合の費用 | 3,000円 | 3,000円 |
| 資本金/th> | 1円~ (平均300万円~) |
1円~ (平均140万円~) |
| 合計 | 216,000円~264,000円(+資本金) | 75,000円~125,000円(+資本金) |
また、株式会社や合同会社の設立には資本金が1円以上必要になります。
しかし、実際には信用性を考え、株式会社なら平均300万円程度、合同会社でも140万円程度の資本金を準備しての起業するケースが大半です。
個人事業主の開業は0円でできましたが、法人化する場合はこうした資金がかかる点を知っておきましょう。
社会保険料の負担が増える
法人化すると、ひとり会社であっても社会保険に強制加入となります。
これにより手厚い保証が受けられる一方で、社会保険料の負担(会社の折半分)が増加する点に注意しましょう。
赤字でも住民税の負担が生じる
法人が納める税金には「法人税」「法人事業税」「法人住民税」などがあります。
このうち法人税、法人事業税、法人住民税の“法人税割”については、赤字であれば費用負担が発生しません。
しかし、法人住民税の“均等割”については、赤字でも関係なく納付義務が発生します。
これは、均等割算定基準が「資本金額、従業員数」となっていて、所得額にかかわらず算定されるためです。
税務処理などの事務作業が煩雑になる
法人の税務処理や会計処理は、個人事業主と比べると複雑です。ひとりで法人化した場合などは、業務と煩雑な事務作業を並行して行わなくてはなりません。
それ以外には経理・会計担当の従業員を雇うか、税理士へ依頼するかといった方法があります。代行してもらうことで負担は軽くなりますが、それぞれ人件費・報酬の支払いが必要になる点に注意しましょう。
法人化を考えるのはいつ?検討のタイミング

個人事業主が法人化するには、総合的なメリット・デメリットを比較したうえで決定することが重要。
ただし、以下のいずれかに当てはまるようなら、法人化を前向きに検討してみてもよいでしょう。
- 年間所得が700万円以上になったら
- 事業の売上が1,000万円を突破したら
- 資金調達をしたいとき
年間所得が700万円以上になったら
個人事業主の年間所得が700~800万円の場合、かかる所得税率は23%です。
一方、法人化していた場合は15%(資本金1億円以下の場合)です。
金額にすれば所得税なら161万円、法人税なら133万円ですので、30万円近い差が生まれることになります。
個人事業主として年間所得が700万円、月の粗利60万円を超えたら、法人化を検討してみて良いでしょう。
事業の売上が1,000万円を突破したら
事業の売上が1,000万円を超えると、2年後から消費税が課税されます。しかし、1,000万円を超えた時点ですぐ法人化すれば、法人化してから2年間は「免税事業者」となれるので、消費税を納付せずにすみます。
ただし、免税事業者になるには資本金額1,000万円未満である必要がある点に注意しましょう。
資金調達をしたいとき
より大きな額の資金調達をしたい場合は、法人化したほうが有利です。
会社として融資や補助金を申請できるようになりますし、株式会社ならば株式の発行により出資を募ることもできます。
法人化に必要な手続きと手順は?

個人事業から法人化に必要な手続きは以下のとおりです。
- 法人登記
- 個人事業の廃業手続き
- 資産、負債の引き継ぎ
- 許認可や契約物(オフィスなど)の名義変更
- 税務署や自治体などへの届け出
1.法人登記
法人化の際には、定款の作成・認証(株式会社の場合のみ)、設立登記申請などの手続きを行います。
2.個人事業の廃業手続き
法人設立後は、すみやかに「廃業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」を作成し、税務署へ提出します。
用紙は国税庁の公式サイトからダウンロードできます。
参考リンク:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁
青色申告をしていた場合は「青色申告の取りやめ届出書」が必要になるなど、同時に提出する書類についても必ず確認しておきましょう。
3.資産、負債の引き継ぎ
個人事業の資産、負債を法人へと引き継ぎます。
【資産の引き継ぎ方法】
- 売買契約:資産を個人→法人へ売却する
- 現物出資:金銭以外の資産を出資する
- 賃貸契約:法人が賃借料を払って個人所有物件を借りる
【債務の移行方法】
- 重畳的債務引受:法人と個人事業主が共同で債務を引き受ける方法
- 免責的債務引受:法人が単独で債務を引き受ける方法
4.許認可や契約物(オフィスなど)の名義変更
許認可を受けている場合や賃貸契約、リースの契約などを利用している場合、それぞれ名義変更を行います。
法人用の銀行口座も開設しましょう。
5.税務署や自治体などへの届け出
法人化したあとは税務署、都道府県・市区町村、年金事務所等への届け出が必要になります。
従業員を雇用する場合は、労働基準監督署、ハローワークにも届け出をします。
個人事業主から法人成りするときの注意点は?

個人事業主から法人成りする際には、注意すべきポイントもあります。
会社→個人事業主に戻ること(個人成り)は難しい
いちど法人成りして会社を設立したあと、個人事業主へ戻ろうとするとかなりの手間とお金がかかります。
①株主総会の開催、会社の解散決議をおこなう
②「解散申告」で事業を停止させる
③「精算申告」登記簿から法人格を消す
④会社の資産を処分し、残った純資産は株主に返金する
⑤法人の消滅完了
⑥事務所・店舗の原状回復、在庫処分など
また会社の廃業に際し、精算申告にかかるお金が41,000円、官報公告に掲載する「廃業公告」で40,000円がかかります。
最低でも合計80,000円以上かかるうえ、税理士や司法書士などに手続きを依頼した場合は依頼料も必要です。
法人成りをしたあとは責任を持って経営をするとともに、廃業にはかなりの労力を割かなくてはならないことを知っておきましょう。
法人成りのタイミングによっては負担やコストだけが増える場合も
法人成りするとさまざまな“税制優遇”がありますが、その一方でコストや経理業務の増加などのリスクもあります。売上があまりないうちに法人成りして、メリットよりデメリットが勝ってしまうのは考えものです。
法人成りする場合は、以下のようなタイミングで検討するとよいでしょう。
- 個人事業の利益が800~900万円になったとき
- 2年前の売上が1,000万円を超えたとき
- 前年の前半6ヶ月の売上が1,000万円超、または人件費が1,000万円超となった場合
- 取引や融資、採用における「信用性」を高めたいとき
個人事業の利益が800~900万円になったとき
個人事業の利益(合計所得)が900万円以上になると、所得税率が「33%」となり、法人成りしたときの法人税率(15~23.2%)よりも納税額が高くなる可能性があります。
また法人成りすれば生命保険料が全額控除できたり、赤字の10年間の繰越ができたりといった経理上のメリットも多く、個人事業主でいるよりも差し引ける控除額が増えます。結果的に節税につながる可能性も高いでしょう。
2年前の売上が1,000万円を超えたとき
その他のタイミングとしては、2年前の売上が1,000万円を超えたとき、法人化を検討するケースも多いでしょう。個人事業主が売上1,000万円を超えると「課税事業者」となり、その年の2年後から消費税の納付義務が発生します。
しかし、資本金1,000万円未満で法人成りすれば、その年から2年後までは免税事業者となります。
前年の前半6ヶ月の売上が1,000万円超、または人件費が1,000万円超となった場合
前年の1~6月の売上が1,000万円を超えるか、人件費が1,000万円を超えた場合は、個人事業主でもその翌年(=今年)から「課税事業者」となります。
しかし、9月1日に法人成りし、決算月を3月にして1期目を7ヶ月にすると、最長2年間は消費税の納付が免除されます。
取引や融資、採用における「信用性」を高めたいとき
個人事業主に比べ、法人は取引・融資・採用においての信用性が高くなります。
そのため、事業展開・拡大などをしたい場合、法人化することでスムーズに戦略を進められるでしょう。
事業が軌道に乗ったら法人化を検討してみよう
法人化すれば税制優遇があり、融資などの資金調達で有利になるメリットは大きいといえます。事業を展開・拡大したいのであれば、法人化をしたほうがなにかとスムーズになるでしょう。
しかし、経理・会計処理が複雑になる点や、資本金の準備、決算公告の義務が生じるなど、場合によってはデメリットのほうが大きくなることも。法人の方が経費も多くかかります。
また事業に失敗した場合も、簡単に会社を畳むことはできません。
法人化について考える場合は、売上や事業の展望、従業員数などさまざまな観点からシミュレーションしてみましょう。そのうえでメリットの方が勝る場合は、法人化を検討してみてはいかがでしょうか。