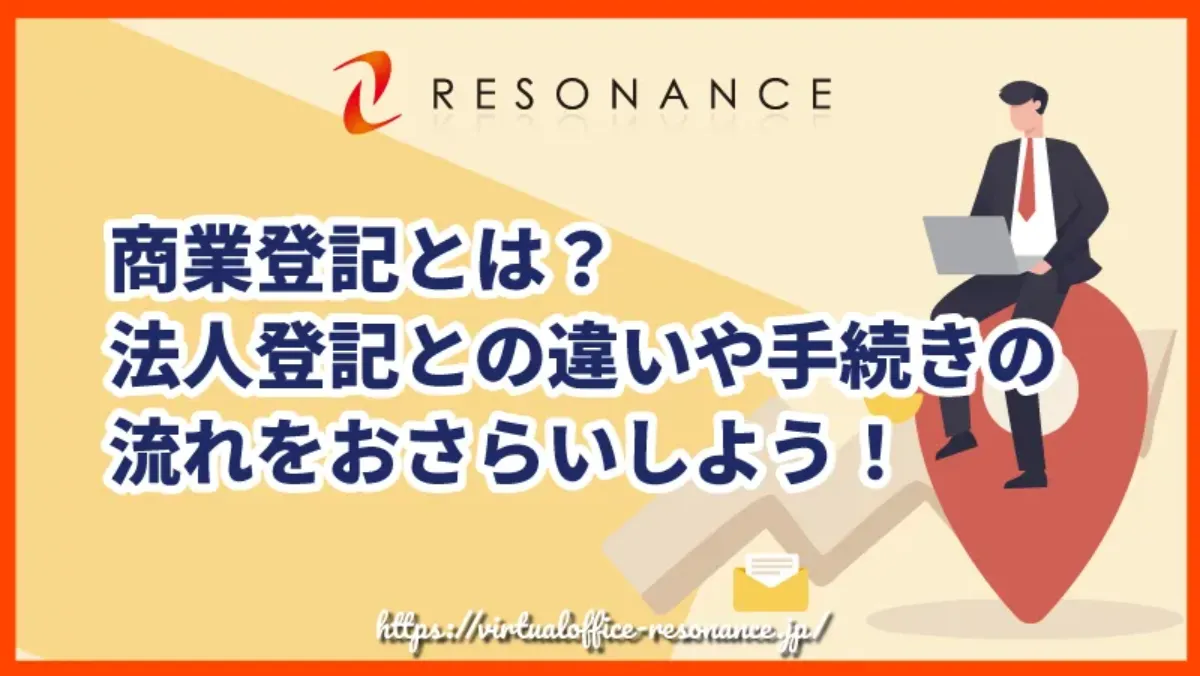起業というと「独立してビジネスを興し、会社を経営する」というスタイルを思い浮かべがちです。しかし最近では、会社員をしながら自身でビジネスを立ち上げる「週末起業」が人気となっています。
本記事では、週末起業のメリット・デメリットやおすすめの業種をまとめてご紹介。また週末起業を失敗させないためのポイントや、独立のタイミングなどについても解説します。
週末起業とは?メリット・デメリットをチェック
週末起業とは「休日などを利用し、本業の会社勤めとは別でビジネスを立ち上げること」を指します。
週末起業が人気となっている理由には、インターネット上でできるビジネスの種類が増えたことが考えられるでしょう。ネットを使えば自宅で気軽に起業できますし、業種によっては小資本でビジネスの立ち上げが可能となります。
言い換えれば、週末起業は「リスクがほぼない状態で起業できる方法」なのです。
よく似た言葉に副業がありますが、週末起業と副業は根本的な部分で異なります。
| 副業 | 本業の合間に別の仕事で副収入を得る |
|---|---|
| 週末起業 | 休日等の時間を利用して事業を興し、副収入を得る |
週末起業のメリット
週末起業のメリットは以下の5つです。
- 会社を辞めずに起業するため、収入が不安定にならない
- 元手(資本)が少なくても始められるため、リスクが低い
- 空いた時間で収入を増やせる
- 自身のやりがい、スキルアップにもつながる
- 週末起業でビジネスが軌道に乗れば、独立も目指せる
「会社員」として安定した月収をもらいつつ休日などに起業をする週末起業は、起業の大きなデメリットである「不安定な生活」を強いられることがありません。
また業種によっては、元手ゼロ(または少額)のスモールスタートで始められる点も週末起業の魅力です。これは「会社員の安定収入があるからこそ、大きなリターン(初期費用の回収)を必要としない」という要素も関係しているでしょう。
自身の手すきの時間で収入アップが目指せるのも、週末起業のメリットです。
そのほかには、やりがいやスキルを獲得できるのも週末起業の魅力だといえます。特に本業と全く違った業種で週末起業した場合、本業では得られないやりがいを感じられたり、スキルが身についたりします。
こうして週末起業が軌道に乗れば独立を目指すこともでき、キャリアの選択肢を増やせるのも利点です。
週末起業のデメリット
メリットの多い週末起業ですが、以下のようなデメリットもあります。
- プライベートの時間をビジネスに費やすため、心身の負担が増える
- 疲れや睡眠不足によって本業に影響が出てしまう場合も
- 会社の規則によってはトラブルに発展するケースがある
週末起業の場合、休日や退勤後の時間をビジネスに使うことになります。これはプライベートの時間を削る必要があり、体や精神面での負担が増えてしまう可能性も。
また週末起業で無理をしてしまうと、疲れや睡眠不足などの影響で本業へ支障が出てしまう可能性もあるでしょう。
そのほか週末起業のデメリットとしては「会社との関係性への影響」も挙げられます。
法的には副業そのものは法律違反ではなく、「就業時間以外の時間の使い方」も個人の自由です。
しかし会社の就業規則で副業を禁じている場合、週末起業がばれると処分の対象となる可能性があります。
また、処分対象ではなくとも、副業や週末起業に対し否定的な考えを持つ人との関係性が悪くなる可能性もあるでしょう。
週末起業を穏便に始めたい場合は、顔出しなしでばれにくい業種を選ぶか、会社や上司等に許可を得てから始めるなどの対策を行いましょう。
週末起業におすすめの起業アイデア6つ!
週末起業が気になっている方の中には、「起業したいけれど何をすればいいのか分からない」という方も多いのではないでしょうか。
ここではおすすめの週末起業アイデアを5つご紹介します。ぜひ参考にしてみてくださいね。
ネットショップの運営
まず週末起業におすすめの業種として挙げられるのが、ネットショップの運営です。ネットショップ運営ではネット上に自分の店舗を開き、商品を販売して収益を得ます。
商品の仕入れから販売、お客様対応まで全てネットを通じて行えるため、会社員の週末起業に適したビジネススタイルだといえるでしょう。
昨今ではネットショッピングをする人が増え続けているため、ビジネスとしての将来性も十分です。
ただし販売利益を得るには、専門性の高い商品を扱うなどの「競合との差別化」が必要になります。
Webライター
Webライターは、Webサイトやメディアに使用する文章を書く仕事です。
現在はコンテンツマーケティングがインターネット業界のトレンドとなっており、企業からの需要も高いため、良い記事を書けば十分な収益が期待できます。
ライティングの案件は、クラウドソーシングを活用すると仕事の受注が可能です。初心者の方は、自身の得意な分野から始めることがおすすめです。
パソコン1台で始められる仕事のため、気になる方は挑戦してみましょう。
プログラミング
プログラミングの知識がある方は、需要の高い人材と言われています。
フリーランスにシステム開発を委託する企業は多いため、開発の案件をこなすことができれば、十分な収益を得ることが可能です。
ライティングの案件と同じく、プログラミングの案件もクラウドソーシング等で広く募集されています。まずはどのような案件があるか一通りリサーチしてみましょう。
スキルに自信がある方は、IT企業に直接営業や提案を行うこともおすすめです。
コンサルタント
コンサルタントは“悩み”“課題”を持つ人へヒアリングを行い、アドバイスをして解決を目指すのが主な職務です。
経営や営業、投資などが有名ですが、最近では恋愛や終活などニッチなジャンルのコンサルタントも登場しています。週末起業家のコンサルタントには、本業の経験やスキルを活かして働く方も多く見られます。
ブログ・アフィリエイト
ブログ及びアフィリエイトとは、自身でブログを立ち上げ、広告収入を得る方法です。
アフィリエイトには「Googleアドセンス」のようにクリックして収益が発生するものと、広告をクリックして商品やサービスの購入・利用につながった時点で収益が発生するものがあります。
アフィリエイトの収益化には半年~1年ほどかかることも多いため、長い目で運営を継続する必要があります。ただし、ブログはストック型の副業として半永久的に収益が発生する可能性もあるビジネスです。
必要な初期費用も少なく、週末起業にも適したビジネスだといえます。
Youtubeのチャンネル運営・動画投稿
近年、週末起業に人気なのが「YouTubeのチャンネル運営・動画投稿」です。
YouTubeでは、動画内に表示する「広告」で収益を得ることができます。再生数の多い動画を生み出し続ければ、継続的な収益を得られるでしょう。実際にYouTubeではさまざまな方が副業として動画投稿を行い、収益化に成功しています。
ただし、広告を貼れるようになるまでには「チャンネル登録者数」「動画再生数」など一定の条件をクリアする必要がある点に要注意です。ファンを増やす動画作りを心掛けるのはもちろん、ブログと同様に継続が重要になるビジネスといえるでしょう。
週末起業のポイント!失敗しないコツ2つ

週末起業を成功させるには、次の2点を意識するとよいでしょう。
スモールステップで「目標」を立てる
起業リスクが低いのは週末起業の利点ですが、その分モチベーションが維持しにくかったり、反対に高い目標を掲げてしまって挫折したりする場合があります。
週末起業を成功させるには、「小さな目標を立て、達成する」というプロセスを繰り返すことが大切です。
たとえば最初は「1ヶ月に3万円の収益」など小さな目標を立て、達成したら少しずつステップアップしていくのです。
このように現実的な目標を立てて達成する、というサイクルを繰り返していくことで、週末起業へのモチベーションアップも期待できるでしょう。
始めるときはお金をかけず、小さく始める
週末起業を始める場合は、なるべく初期費用の少ない方法で始めることをおすすめします。
多額の資金をかけて週末起業しても、ビジネスが途中で頓挫した場合は回収しきれず、そのままマイナスになってしまう可能性が高いからです。
極力資金の負担を減らして週末起業をすれば、「ビジネスが上手くいかず中断したい……」という場合も簡単に中断したり、方向転換したりすることができます。
低いリスクでスタートでき、収益を得られる週末起業方法を考えてみましょう。
週末起業の成功事例を3パターン紹介!
週末起業の成功率を高めるためには、実際の成功事例を知ることが欠かせません。成功事例からさまざまなことを学びつつ、自身の事業に活かすことが大切です。
ここでは、週末起業の成功事例を3つ紹介します。週末起業に挑戦したいと考えている方は、それぞれの成功事例を参考にしてください。
技術を活かしてホームページを運営した事例
ITに関係のない職業で働いていたAさんは、趣味のゲームを題材としたブログを運営しています。はじめは日記程度にテクニックや攻略情報を更新していましたが、独学でSEO対策やコンテンツ制作を学んだ結果、アクセス数を伸ばすことに成功しました。
アクセスが伸び始めることに喜びを感じたAさんは、本格的にWebメディアを運営することになり、現在では自身が学んだ知識や技術を教える立場でも活躍しています。
本業で収入を得ながら好きなことを突き詰めた結果、週末起業に成功した事例です。
マーケティングの知識を活かしてネットショップを運営した事例
Bさんは、広告代理店でマーケターとして働き、企業のマーケティングを支援していました。「いずれは独立してネットショップを運営したい」と考えていた中で、友人からネットショップの運営を頼まれたことが、週末起業をするきっかけです。
友人のネットショップは見栄えが悪く、商品も探しにくい仕様となっていたため、マーケティングの知識を活かしてサイトをリニューアルしました。その結果、サイトの視認性が高まっただけでなく、ネット広告や販促企画も活用して売り上げを伸ばすことができました。
週末起業は1人の力でできることが限られるため、お互いの強みを補完できるパートナーと協力することもポイントです。相乗効果が発揮されて成功したモデルケースとなります。
資格を活かしてコンサルタントを行った事例
ITコンサルティング企業で働いていたCさんは、自分なりのコンセプトでサービス提供を行いたいと考えていました。まずは簡単に起業を始めたいと思ったことが、週末起業を始めるきっかけです。
コンサルティングに必要なITコーディネーターの資格、および関連資格を複数所持していたCさんは、知識と肩書きを活かしてインターネットで集客を行います。
専門性が高く評価されたため、週末限定でも依頼したいという顧客が見つかり、順調に依頼をこなして独立を決意しました。
独立のリスクが気になり前に踏み出せない方が、週末起業で収入を確保しながら独立開業まで辿り着いた成功例です。
週末起業で独立したい場合、どのタイミングがベスト?
「週末起業で始めたビジネスで独立したい」という場合、独立のタイミングは人により異なります。
多くの週末起業家は「本業の収入<週末起業ビジネスの収入」となったときに独立を決意しているようです。
また、週末起業家には「起業後半年経ってから」「1年続けられたら」というように“期間”を基準にしている方も多く見られます。慎重派・計画派の方は、自分で定めた期間中にビジネスの将来性や収入を判断し、独立するかを決めても良いかもしれません。
週末起業で収入とやりがいをゲット!小さく始めて育てよう

会社を立ち上げて起業しようとすると、それなりの資金や準備が必要になります。しかし自宅でできる週末起業なら、スタート資金もそこまで必要なく、気軽にトライできるでしょう。
ちなみに自宅での週末起業には、自宅住所公開のリスクがある点に要注意です。
たとえばネットショップを開業した場合、「特定商取引法に基づく表記」という法律によりショップオーナーの住所・氏名・電話番号などを記載しなければならないのです。
知らない第三者に住所等のプライベートな情報を知られたくない場合は、「バーチャルオフィス」を活用されることをおすすめします。
レゾナンスでは、月額990円~(税込)借りられるバーチャルオフィスを提供しております。
格安のため、なるべくコストをかけたくない週末起業にもぴったりです。
またご利用いただける住所は都心の一等地住所となるため、事業のブランディング、イメージアップにもつながります。
「安全に週末起業がしたい」「副業として会社に知られないよう週末起業がしたい」という方は、ぜひバーチャルオフィスのご利用を検討してみてくださいね。