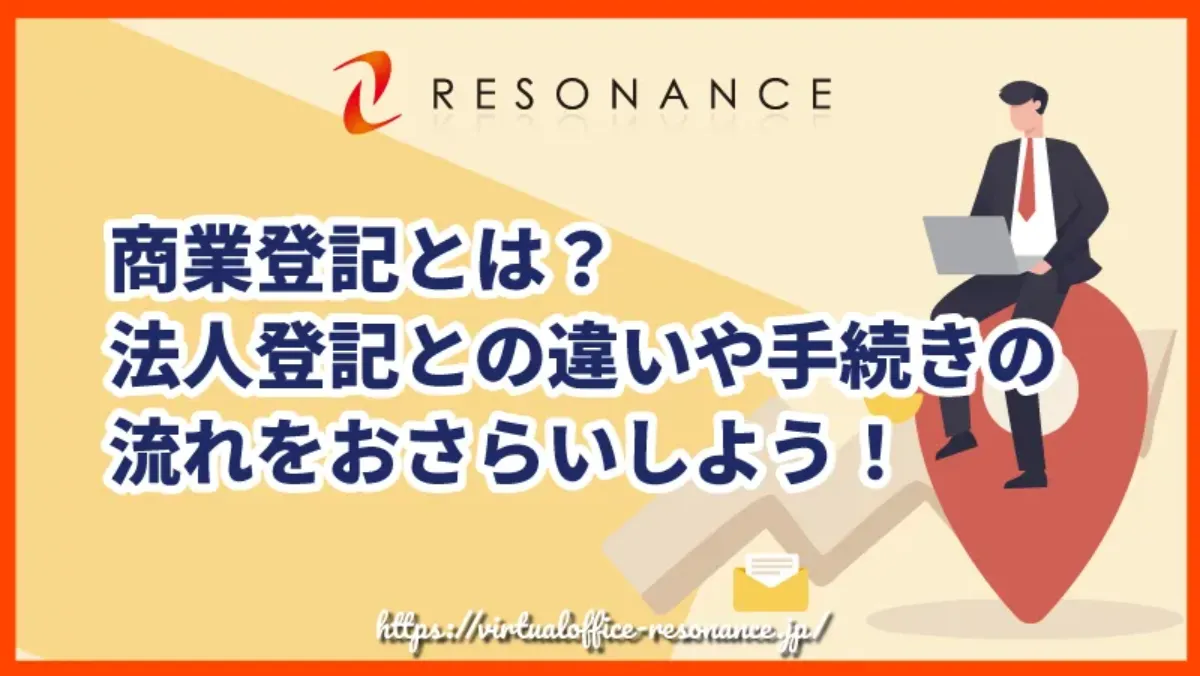新たな働き方を模索する方が増えている昨今、「個人事業主」として開業を考える方も増加傾向にあります。もしこれから個人事業主となった場合、どんなメリットが得られるのでしょうか。
ここでは「個人事業主として事業を始めたい」という方に向け、個人事業主になるメリットやデメリット、フリーランス・自営業・会社員・法人との違いについてご紹介します。
個人事業主とは?

個人事業主とは「開業届を出し、個人で事業を営む人」のことを指します。
そのため副業でビジネスを行っている人やフリーランス、扶養範囲内で事業を行う主婦・主夫の方でも、開業届を税務署に提出したら、その時点で「個人事業主」として開業することができます。厳密にいえば開業してから1ヵ月以内に提出すればいいことになっています。
開業日は厳密に決まっているわけではなく、提出した日から1ヵ月前を開業日にすればいいのです。確定申告時期の前年度の1月~12月の所得を計算し、確定申告をして所得税を納税します。また所得に応じて個人事業税や消費税の納税が必要なケースもあります。
個人事業主になる4つのメリットとは?
個人事業主になった場合、「自由な働き方ができる」というのはなんとなくイメージがつくでしょう。時間や場所、年齢に縛られず働けるメリットは魅力的ですよね。それ以外には、どのようなメリットがあるのでしょうか。
個人事業主になって得られるメリットは、以下の4つです。
①初期費用なしで事業を始められる
法人として起業する場合、最低でも約10万~25万円の費用がかかります。
しかし個人事業主の場合は、開業届を税務署へ提出するだけです。提出は無料なため、初期費用なしで個人事業主として開業できます。副業から開業する場合などには大きなメリットだといえるでしょう。
②青色申告で節税効果が高くなる
個人事業主になった場合、確定申告時に「青色申告」を選択できるメリットもあります。
確定申告の方法には「白色申告」と、個人事業主でないと利用できない「青色申告」があり、それぞれ所得から差し引かれる「控除額」が異なります。
- 白色申告
- 青色申告
基礎控除48万円のみ(所得2,400万円以下の場合)、開業しなくても利用可能
基礎控除48万円+青色申告特別控除55~65万円=最大113万円の控除。
利用するには開業し個人事業主になること、及び税務署へ青色申告承認申請書を提出する必要あり。
※青色申告でe-TAXの利用、または電子帳簿保存を行う場合は65万円の特別控除が受けられます。
紙の書類での直接提出、及び郵送提出は55万円の特別控除となります。
個人事業主として青色申告を選び、特別控除を受けられるようになれば、課税される所得額も低くなります。
高い節税効果が得られるのは、開業した個人事業主ならではのメリットといえるでしょう。
③赤字の繰り越しや損益通算が可能
個人事業主となり青色申告を選択した場合、赤字になった年の損失を次の年に繰り越すことができます(最大3年)。つまり黒字の収益と相殺し、課税所得が少なくなるメリットがあるのです。
また、個人事業主は「損益通算」ができるのも大きなメリットです。たとえば本業で会社員をしつつ副業をする場合、副業で出た赤字を本業分の給与・賞与収入から差し引くことができるのです。
損益通算をして課税所得が減ることになれば、節税のメリットが得られます。
④仕事に使ったものを経費として計上できる
個人事業主になると、仕事に使用したお金や家族へ支払った給与を「経費」として計上できるのもメリットです。
個人事業主の課税額は、総収入に対し各種控除や経費を差し引いた金額で計算されます。家族へ給与を支払っている場合は「青色事業専従者給与」として、支払った給与額を経費扱いにできるのです。
節税のメリットが大きいことから、事業を本格的に行う場合は家族を従業員にすることも検討して良いでしょう。
個人事業主になるデメリットは?
個人事業主にはメリットが多い一方で、当然デメリットもあります。個人事業主になるデメリットとしては、次の3つが挙げられます。
①帳簿付けの手間が発生する
青色申告を選択した個人事業主は、基本的に自身で帳簿付けをしなくてはならないのがデメリットです。青色申告の帳簿付けは「複式簿記」を利用しており、白色申告に比べると煩雑さを感じる場合もあるでしょう。
ただし近年では個人事業主向けの帳簿付けツール(freee会計、やよいの青色申告オンラインなど)も登場しています。帳簿付けを簡単に行える機能が多数揃っているため、ぜひ活用してみてください。
②失業保険が受給できない
個人事業主は「従業員」ではないため、雇用保険に加入できないデメリットがあります。万が一仕事を失っても、失業保険の受給等の就業支援が受けられない点に注意が必要です。
③収入が安定しにくいことも多い
個人事業主として独立した場合、能力次第では大幅な収入アップも夢ではありません。
しかしその一方で、顧客を獲得できなくなると収入が激減するリスクがある点も無視してはならないでしょう。
特に個人事業主として開業したての時期は、会社員に比べると収入が安定しにくい傾向にあります。個人事業主になる際は、こうしたデメリットも知ったうえで検討するようにしましょう。
個人事業主とフリーランスの違いは?

個人で仕事を請け負っている人を個人事業主ということもフリーランスということもあります。具体的に個人事業主とフリーランスはどのように違うのでしょうか。個人事業主とフリーランスは実は似ているようで全く違います。以下で詳しく説明していきます。
フリーランスとは、あくまで「契約形態」を指す言葉
フリーランスとはあくまで仕事の依頼をうけて契約をするときの契約形態に過ぎません。そのためフリーランスとよばれるのは、法律による区分でしかないのです。
個人事業主が税法上の区分を意味しているため、まずこの点が大きく違うのです。
個人事業主とフリーランスの関係性の整理
フリーランスは契約形態の一種であることから、個人だけでなく法人である可能性もあります。個人事業主がフリーランスといった働き方をすることや、会社に属していないフリーランスの法人化は可能となります。
つまりフリーランスといった働き方の中には、個人、個人事業主、法人が含まれるということです。
個人事業主と自営業の違いとは?
自分で経営するという意味では、自営業も個人事業主も同じです。そのためフリーランス以上に自営業は個人事業主と混合されることが多いです。それでは個人事業主と自営業はどのように違うのでしょうか。
自営業とは自分で事業をおこなって収入を得ている人のことをいうので、個人事業主であっても会社経営者であっても自営業です。逆に言えば自営業といっても、個人事業主とは限らないということです。
また副業であっても事業をしているようであれば、自営業と呼ぶこともあります。自営業自体にはっきりとした定義があるわけではないので、多少ニュアンスが異なることはありますが、一般的に自分で事業をおこなっていれば会社経営であっても個人事業主であっても自営業です。
個人事業主と会社員の違いとは?
それでは税金、社会保険料や収入面といった観点で個人事業主と会社員の比較をしていきます。
税金を収める際の違い
会社員の場合は税金は天引きとなるため、手続きをする必要はありません。しかし個人事業主の場合はすべて自分で処理をして、確定申告まで進める必要があります。
また会社員と個人事業主では税金の種類が違うので、良く把握しておく必要があります。そのため必ずしもどちらが税金が安いということはいえないのです。
社会保険料の支払いの違い
会社員になると社会保険料は税金とともに給与から天引きとなります。しかし雇用主と金額は半々になります。しかし個人事業主の場合は国民保険に全額自分で支払いをする必要があります。
個人でも会社経営をすると、社会保険に加入することができますが全額自分で負担をする必要があります。
収入面の違い
会社員は会社で決められた給与を受け取ることになります。インセンティブや昇給などはありますが、いきなり大きな収入を得られることは多くありません。しかしいきなり大きく収入が減ったり配属している限り収入がゼロということはないでしょう。
個人事業主の場合は利益はそのまますべて収入になります。仕事の受注はすべて自分で決めることができ、収入の上限はとくにありません。しかし仕事がなくなればいっきに収入がゼロ、利益という面ではマイナスということもあります。
そのため安定感があるのは会社員であり、自分の実績が収入に直結するのが個人事業主だということです。
個人事業主の場合、体調悪化や入院などで仕事ができなくなっても有給休暇のような補償はがないのがデメリットです。個人事業主向けの休業補償がある保険に加入するなど工夫する方法はあります。
働き方の違い
会社員として働く方法は、それぞれの会社に準じた働き方となります。労働基準法に則った範囲で、就業時間や就業内容、休みの日などは会社の規則に従うことになります。
しかし個人事業主はすべて自分で決めることができます。特に自宅兼事務所にしている人は、仕事とプライベートの時間の境目がない人も少なくはないでしょう。この働き方があうかどうかはそれぞれの人次第です。自分で色々決めたい人には、個人事業主の方が向いています。
また仕事の数も個人事業主は調節することができます。努力次第でもっと案件をもらうこともできますし、減らすこともできます。会社員としては、ある程度会社で決められているので自分のペースで仕事をできることは多くありません。
個人事業主と法人の違いは?
個人事業主とよく比較されるのが「法人」です。
簡単に説明すれば個人事業主は「会社を興さず個人で事業を行うこと」を指し、法人は「会社を設立する」という違いですが、細かい部分に注目するとさまざまな違いがあります。
| 個人事業主 | 法人 | |
|---|---|---|
| 事業スタート時の手続き | 開業届(及び青色申告承認申請書)の提出のみ | 法人登記 (会社印や各種書類が必要) |
| 事業開始の初期費用 | 0円 | 法定費用と資本金が必要
|
| 事業を廃止する時の手続き | 廃業届を提出する | 解散登記、及び公告を要する ※数万円の費用負担あり |
| 納付する税金の種類 |
所得税率は5~40% |
普通法人の法人税率は |
| 経費計上の範囲 | 事業にかかる範囲のみ計上可 ※自身への給与、生命保険料は経費とならない |
事業にかかる費用に加え
なども経費の対象 |
| 赤字の繰り越し可能期間 | 青色申告ならば3年間 | 10年間 |
| 経理・会計の方法 | 個人で確定申告を行う | 法人決算書による申告 |
| 社会的信用度 | 低 | 高 |
| 社会保険の負担 | 5人未満の場合は事業者負担なし | 会社負担が必要 |
事業開始・設立時の手続き・費用の違い
個人事業主と法人の大きな違いは設立時の手続きや費用の違いです。法人は個人事業主と比べて設立時の手続きが大変で初期費用がかかるため、個人事業主として設立する場合が多いです。
法人を設立する場合登記や定款などを作成する必要があり、さらに設立費用として20~30万円が必要になります。個人事業主は開業届を税務署に提出すれば手続き終了のため、費用も手間もほとんどかけることはありません。
廃業時の手続きの違い
廃業手続きも開設の時とおなじように個人事業主の場合は税務署に届け出を出すだけです。しかし法人は解散手続きや清算の登記などするべき手続きが多く、費用もかかります。
もし従業員がいる場合は、まずは従業員に対して通知をする必要があります。廃業挨拶状とよばれる書面であり、従業員も生活があることからできるだけ早くに通知するようにしてください。
次に株主総会において解散決議をする必要があるのですが、自主的に廃業をする場合は株主数の3分の2が同意する必要があります。さらに清算人の設定もこの時点で必要です。
解散決議が終わると、会社廃業と清算人選任をした旨を登記する必要があります。登記解散と清算人選任登記は法務局にて行います。また会社を廃業するには、法人税、住民税、事業税に関する解散の届け出である異動届書の提出を税務署や役所などに行います。ハローワークに雇用保険の、年金事務所や協会けんぽに社会保険jの、労働基準監督署に労働保険に関しての届け出が必要です。
さらに許認可が必要な業種に関しては、それぞれの行政機関に廃業手続きをするようにしてください。
ここまで届け出が終わったら、官報にて解散広告が必要になります。もし借金がある場合は、債権者にお金を返してもらうことが必要です。最後に2回の決算書類を作成し、株主総会において承認をしてもらい、残りの財産や債務などの整理をします。これが終わったら解散決定報告と清算決了をして廃業になります。
法人を廃業するためにはこれだけの手続きが必要であり、さらに以下のような費用が必要になります。
| 解散登記をする際の登録免許税 | 30,000円 |
|---|---|
| 清算人選任登記の登録免許税 | 9,000円 |
| 清算結了登記 | 2,000円 |
| 2通の登記簿謄本 | 1,200円 |
| 印鑑証明書 | 450円 |
| 官報公告料 | 32,000円 |
支払う税金の額や仕組みの違い
個人事業主と法人では、支払う税金の額や仕組みが違います。よく税金も法人の方が高いといわれますが、実は利益の額によってどちらの方が税金が高いかは異なってきます。
個人事業主は累進課税とうよばれる仕組みとなっており、所得が高くなればなるほど税率が高くなる制度となっています。所得額によっては所得税、住民税を加えた金額は所得の50%を超えることがあり、法人税より高くなるケースがあるのです。
個人事業主にかかる所得と税金は以下のようになります。所得が少ない場合は税率も低いのですが、所得が高い場合は税率はどんどんあがっていき所得が4,000万円を超える場合は所得税率だけで45%となります。これに市民税が加わるので、50%を超えるということです。
| 所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円を超え330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円を超え695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円を超え900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円を超え1800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
法人税は個人事業主ほど所得によっての税率の変動はありません。
| 区分 | 適用関係(開始事業年度) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平28.4.1以後 | 平30.4.1以後 | 平31.4.1以後 | ||||
| 普通法人 | 資本金1億円以下の法人など | 年800万円以下の部分 | 下記以外の法人 | 15% | 15% | 15% |
| 適用除外事業者 | 19% | |||||
| 年800万円超の部分 | 23.40% | 23.20% | 23.20% | |||
| 上記以外の普通法人 | 23.40% | 23.20% | 23.20% | |||
引用:国税庁
以上のように所得が少ない場合は個人事業主の方が税率が低いですが、一定の所得を超えると法人税の方が税率が低いということになります。
個人事業主か法人で迷ったらどうやって決める?
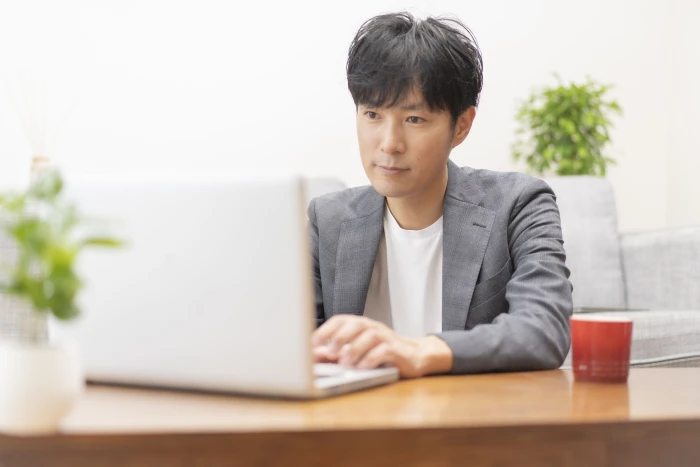
個人事業主と法人は、税金の種類、初期費用、開業までに必要なことなど全く違います。
まず初期費用や開業までの手続きは圧倒的に法人の方が負担が大きいです。しかし法人の方が社会的に信頼度があり、さらに収入額によっては法人税の方が税率が低くなることもあります。
全体的にこれらを考慮してから考えるようにしてください。または個人事業主として開業し、ある程度の収入を得られるようになってから法人化する方法もあります。
個人事業を始める前にしておくと良いこと
個人事業を始める前に、いくつかしておくべきことがあります。これらは必須ではないのですが、やっておくのとしないのではあとから大きく変わってくることがあります。
クレジットカードや住宅ローンを契約しておく
クレジットカードの申し込みや住宅ローンの契約は会社員時代にしておくようにしてください。会社をやめて個人事業主としてまだ実績がない時は審査に通りにくいためです。
社会人であれば安定した収入があればあまり審査に落ちることはありません。
事業計画を立てる
個人事業といっても、現在ではさまざまな事業があります。そのため「どのようなことができるのか」「そのために必要はスキルはあるのか」「どのような目標をたてるのか」など具体的に事業計画を立てることが重要です。
また事業内容によって初期費用がかかることもあるので、さらに事業を始めるまえに準備が必要となります。しかし完全にメインの事業を決めないで、色々と試していくことができるのが個人事業主の良さでもあります。例えばまだ継続するかわからない時点では雑所得で確定申告をして、ある程度軌道に乗ってから事業所得に変更して確定申告をする方法があります。
個人事業主になる際に必要な手続き
個人事業主になるためには、いくつか必要な手続きがあります。それぞれ詳しく説明していきます。
税務署に開業届を提出する
個人事業主になるのは難しいことではなく、税務署に開業届を出せば終わりです。開業届は一枚の用紙であり、記入するのも難しいわけではありません。
開業届の書き方について、くわしくはこちらの記事をお読みください。
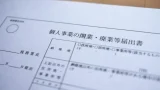
社会保険に関して必要な手続き
個人事業主は国民健康保険への加入、もしくはこれまでに勤めていた企業の会社保険を任意継続するかのいずれかの方法となります。また国民年金への加入が必要です。
青色申告をする場合は「青色申告承認申請書」を提出
個人事業主として開業する場合、毎年確定申告をする必要があります。確定申告は青色申告と白色申告があるのですが、青色申告は最大50万円控除をすることができるのでおすすめです。
青色申告で申告には、前もって青色申告承認申請書を提出する必要があります。これは確定申告の時ではなく、開業届を出したときに提出するようにしてください。
名刺やホームページを作成する
開業をしてから忙しくなるため、名刺やホームページは前もって作っておくことをおすすめします。これらを作るためには費用がかかるため、会社員をしながら少しずつそろえていくといいでしょう。
ホームページは業者に依頼する他、自分でも簡単に作成することができます。低額でブログ感覚で画像などをアップするだけパソコンのスキルを必要としないサービスが多いです。しかし他業者と差をつけるためには、しっかりとオリジナルのホームページを作るのをおすすめします。
特に商品をきれいに見せたい場合は、ある程度ホームページに初期費用をかけることも必要でしょう。
個人事業主が使える給付金・補助金制度
個人事業主として開業するさいに、給付金や補助金制度を利用することができます。特に以下の3つの給付金や補助金制度は知っておくとよいでしょう。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者が経営計画を策定することにより、販路開拓への取り組みを支援する補助金です。補助率は2/3、補助額は上限で50万円となっており補助対象はチラシ作成、広告掲載また店舗の改装となります。
さらに低感染リスク型ビジネス枠として、コロナ社会に対応してテイクアウトやECサイトを構築する際、必要な費用の3/4、上限100万円まで補助をします。
参考:持続化補助金について(独立行政法人中小企業基盤整備機構)
ものづくり・商業・サービス補助金
中小企業がインボイス導入や賃金の値上げ、働き方改革に対して対応するために必要な開発や設備投資などに対して以下のような補助を受けることができます。
補助上限
[一般型]1,000万円
[グローバル展開型]3,000万円
補助率[通常枠]1/2、小規模企業者・小規模事業者2/3
[低感染リスク型ビジネス枠] 2/3補助要件
以下を満たす3~5年の事業計画の策定及び実行
・付加価値額+3%以上/年
・給与支給総額+1.5%以上/年
・事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円
IT導入補助金
ITツールを導入するすることにより、定期的なルーティーンワークをシステムに任せて従業員の負担を減らしたり、業務効率化につなげることができます。この他ITツールを導入することで、業務の改善につなげている、またつなげる予定のある企業はIT導入補助金を受け取ることができます。
ITツールは在庫管理、経理業務の効率化、顧客管理、営業な管理などさまざまな業務に利用することができます。
参考:IT導入補助金
| 通常枠 | 低感染リスクビジネス枠 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | A類型 | B類型 | C類型-1 | C類型-2 | D類型 |
| 補助金申請額 | 30万~150万円未満 | 150万~450万円以下 | 30万~300万円未満 | 300万~450万円以下 | 30万~150万円以下 |
| 補助率 | 1/2以内 | 2/3以内 | |||
引用:IT導入補助金
個人事業主が支払う必要のある税金の種類
個人事業主が支払う必要のある税金は、以下のようなものがあります。
所得税
所得税は前年度の1月~12月の間の総収入から経費の総額を引いた金額となります。経費によって利益額はかなりかわり所得税にも大きく影響があります。そのため節税のためには、経費になるものはしっかりと申告することが重要です。
直接仕事に必要な物以外にも、仕事で使っている部屋の電気代や水道代、携帯料金、Wi-Fi料金なども経費として申告できます。プライベートでも仕事でも使っている場合は、仕事で使っている割合を設定して申告します。
超過累進課税とは?
累進課税制度には単純累進課税と、超過累進課税の2種類の方式があります。
単純累進課税は課税標準が一定額を超えた場合に、その全体に対して高い税率を適用するというもので、超過累進課税は課税標準が一定額を超えた場合に、その超えた金額に対してのみ、高い税率を適用するというものです。
(現在用いられているのは、超過累進課税方式です)
住民税
所得税に応じて住民税が決まります。確定申告が終わった後、市町村から住民税の納付書が届きますので支払う必要があります。支払い方法は6月、8月、10月、1日の4回払いと6月に一括で支払う方法があります。
消費税
消費税を支払う対象となるのは、前前年の売り上げが1,000万円を超えた場合に必要になります。また開業以降2年目であっても、前年の1月1日~6月30日の期間の売り上げが1,000万円を超えた場合は消費税の支払いが必要になります。
個人事業税
個人事業税は8月と11月の年2回都道府県に対して納付をします。事業所得が290万円を超える場合に個人事業税が発生するのですが、課税対象となる業種とならない業種があります。
この所得とは収入から経費をひいた金額になります。
自宅でビジネスをする個人事業主はバーチャルオフィスの活用を!
近年では自宅で行っていた副業をきっかけに、個人事業主となる方も増えています。
しかしご自宅で個人事業を行う場合、どうしても「自宅住所の公開リスク」が伴うデメリットがあります。
プライバシーを守りながら個人事業主として働きたい方は、バーチャルオフィス(事業用レンタル住所)を活用されると良いでしょう。
レゾナンスでは、月額990円~(税込)で一等地の住所がご利用可能なバーチャルオフィスをご用意しております。ご住所は東京都港区浜松町、港区青山、中央区銀座、中央区日本橋、渋谷区神南、渋谷区神宮前、渋谷区恵比寿、新宿区西新宿、千代田区神田、横浜市西区から選べて、かつ法人登記も可能です。
またバーチャルオフィスの住所は、Webサイトや名刺にも記載ができます。一等地の住所をオフィスの住所としてご利用いただけるため、事業のイメージアップにも効果的です。
ご自宅のプライバシーが気になる個人事業主様はもちろん、「開業コストを抑えたい」「東京の住所が使いたい」という方は、ぜひレゾナンスのバーチャルオフィスをご検討くださいませ。