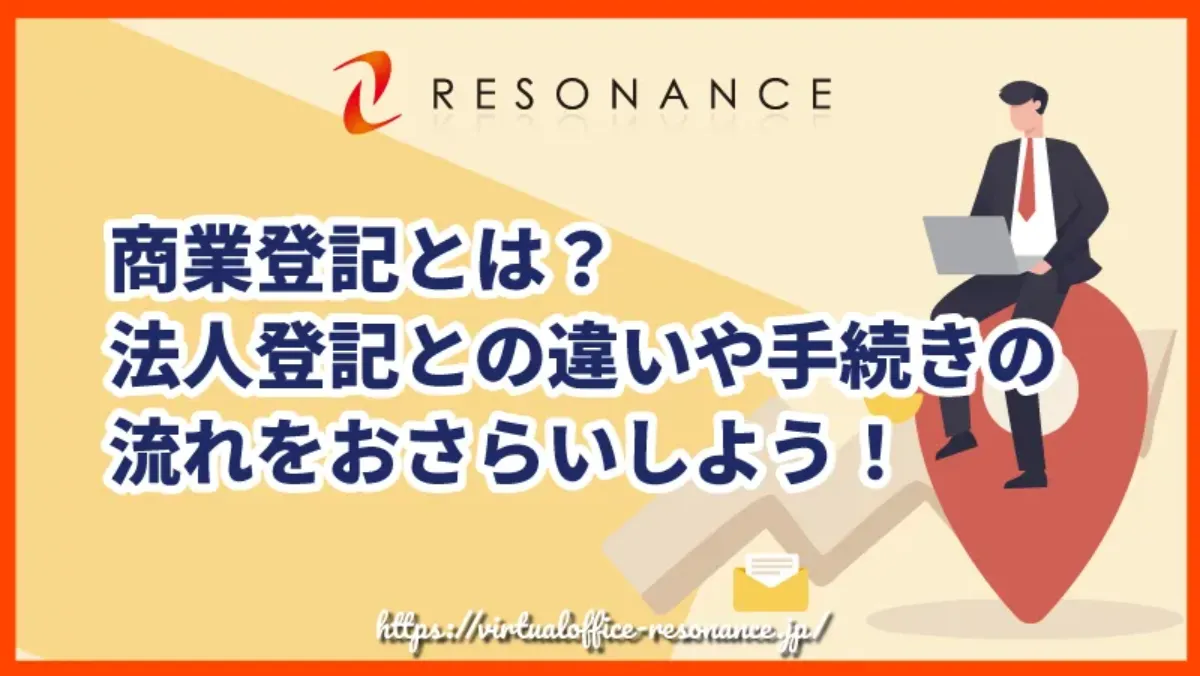個人事業主としてビジネスを始めたけれど、屋号をつけるべきかどうか悩んでいませんか?
個人事業主は、開業時などに「屋号」を決められます。
屋号は「会社名」のように必ずつけなければいけないものではなく、あくまでも“任意”です。
よって、屋号を付けずに事業を行っている個人事業主も多く見られます。
とはいえ、皆さんの中には「屋号をつけないと、何かデメリットがあるのでは?」と気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは、個人事業主が屋号なしで事業をするデメリットや、屋号をつけるメリットを解説。屋号を届け出るタイミングや後からつける方法、決め方のポイントもご紹介します。
屋号とは会社法人でいう会社名(商号)のこと

屋号とは、個人事業主が事業につける名前です。
会社法人でいうところの「会社名(商号)」の個人事業主版とも言い換えられます。
○○屋、ショップ○○
○○サロン
○○事務所
オフィス○○
○○チャンネル(動画配信など)
原則として個人名とは別に設ける名称であり、ビジネスの連絡先や宣伝、銀行口座開設時などに使用することができます。ただし執筆家などクリエイティブ関連のフリーランスにおいては、ペンネーム(雅号)を屋号として登録するケースもあります。
屋号をつけるかどうかは任意であり、屋号なしでも個人事業主として活動することは可能です。屋号をつけないからといって罰則があるわけでもありません。
また開業時に屋号をつけなかったとしても、後からいつでも屋号をつけることができます。

屋号も会社名も、ビジネスで使用する名称であること、使用するには申請が必要であることがそれぞれ共通しています。ただし会社名の場合は、法人登記を行う際に必ず登録する義務があるという違いがあります。
また屋号は登録・変更をしたい場合無料で手続きできますが、会社名を登録・変更するには登録免許税などの費用が必要です。
【屋号と会社名の違いをまとめた比較表】
| 屋号 | 会社名(商号) | |
|---|---|---|
| 決定の義務 | なし(任意) | あり(登記時に登録) |
| 法律上の扱い | 法人格の名称 | 事業そのものにつける名前 |
| 登録のタイミング | 開業時または確定申告等 ※開業以降も随時登録可能 |
登記時 |
| 変更時の費用 | 無料 | 登録免許税30,000円~ ※司法書士に依頼する場合は報酬も必要 |
| 肩書 | 事業内容に応じた肩書を登録可能 (○○屋、○○サロン、○○事務所など) |
会社形態に応じた名称にする義務あり (株式会社○○、○○株式会社など) |
個人事業主やフリーランスが屋号なし(個人名)で活動するリスクは?

個人事業主が開業するにあたり、屋号の記入はあくまでも任意であり、義務ではありません。また屋号登録していなくとも、屋号としてショップ名等を名乗ることも法的には問題ない行為です。
そのため屋号なし(個人名)で開業する“だけ”ならば、リスクは低いといってよいでしょう。
ただし、状況次第では税務署へ屋号を登録しておく必要があるのも事実です。
例えば屋号入りの個人事業用口座を開設したい場合や、融資を受けたい場合などは、申し込みをする際に必要書類として「屋号が記載された開業届の控え」が必要になります。
そのためには事前に手続きを行い、税務署のデータとして屋号を登録しておく必要があるのです。
屋号入り口座や融資は、事業拡大をする上で必要になる場合も多いものです。
また屋号があると事業を認知してもらう機会も増えやすくなります。
このため、事業を大きく育てたい方にとっては「屋号なしでいると機会損失を生む可能性が高い」とも考えられるでしょう。
【屋号についての関連リンク】

個人事業主やフリーランスが屋号なしでいるメリット・デメリット

先の項でもご説明したとおり、小規模な事業規模であれば、屋号をつけなくても大きなデメリットはありません。
特にクライアントワークを中心にお仕事をされている場合などは、屋号をアピールする機会も少ないので、屋号なしでもさほど問題ないでしょう。
ただし屋号を登録していない場合、屋号ありの場合に比べると少々不便になることはあります。
屋号なしのメリット
屋号なしで活動するメリットは以下の2つです。
- 屋号を考える手間や時間がかからない
- 商標権の侵害などを考慮する必要がない
屋号を考える際には「事業に合う屋号」であることはもちろん、他の会社名や屋号と重複していないかを調べる、表記方法を考えるなどの手間と時間が生じます。
屋号なしで活動する場合、こうした手間や時間が発生せず、仕事にのみ集中することができます。
また、屋号が商標登録された名称と重複していると損害賠償請求などのリスクがありますが、個人名など屋号なしで活動するのであれば、そのようなリスクも発生しません。
屋号なしのデメリット
屋号なしのデメリットはいくつかありますが、比較的大きなデメリットとしては「信用されにくいこと」が挙げられます。
- 社会的な信用が低く見られがち
- 事業内容が伝わりにくく、営業・販促面で不利になる場合がある
- 事業用の銀行口座や融資の利用ができない可能性が高い
同じ事業を行っていても、個人名のまま活動するより「〇〇デザイン事務所 代表 田中△太」というふうに屋号表記のほうが対外的な信用度は高くなります。
よって屋号なしのままでは、信用されにくくなるおそれがあるのです。加えて個人名のままだと事業内容がわかりにくく、利用や受注につながりにくいことがあるかもしれません。
また、個人事業主が利用できる屋号入りの銀行口座や融資等も屋号なしでは利用できない場合が多く、事業活動に制限が出てしまうおそれもあるでしょう。
これらデメリットは小規模な事業活動においてはさほど問題がないのですが、事業規模が大きくなるほど弊害になる可能性が高いです。
個人事業主やフリーランスが屋号をつけるメリットは?

先述のとおり、屋号付けについては任意となります。
一方、個人事業主が屋号をつけた場合は、事業を営むうえでさまざまなメリットが得られます。
事業内容が伝わりやすい

個人事業を営むにあたって「事業内容が伝わりやすいか」というのはかなり重要です。
たとえばネイルサロンを経営している場合、個人名で活動をしていると第三者に「何の事業をしているのか」が伝わりにくいですが、「ネイルサロン○○」というふうに屋号をつけておけば一目で事業内容を理解してもらえます。
また、屋号をつけているとチラシや名刺などの販促ツールに掲載することもできます。屋号と事業をセットでアピールすることで顧客の印象に残りやすくなり、顧客の開拓や新規獲得などの効果が期待できるでしょう。
【名刺への屋号の記入例】


【チラシへの屋号の記入例】


金融機関で屋号入りの口座を作ることができる

個人事業主が屋号をつける2つ目のメリットは、銀行などの金融機関で屋号入りの銀行口座を開設できる点です。
具体的にいえば「屋号と個人名を両方記載した銀行口座」となりますが、屋号が入ることで入金者(顧客など)からの対外的な印象も良くなり、信用を得やすくなるでしょう。
特に、直接対面して取引を行うわけではないネットショップ等のビジネスにおいては、こうした「顧客が得られる情報から判断できる信用性の積み重ね」が重要な要素となります。
- みずほ銀行
- PayPay銀行
- 住信SBI ネット銀行
- ゆうちょ銀行
- 三菱UFJ銀行
- りそな銀行
- 三井住友銀行
- その他信用金庫、地方銀行 等
また屋号入りの事業用銀行口座を持つことで、プライベート口座や別の事業用口座との区別が付けやすくなるメリットもあります。
その事業だけに使う口座ゆえ、事業でいつ誰からお金が入り、経費として何に使ったのかという“お金の流れ”もわかりやすくなります。
これにより「プライベートで使ったお金を間違って経費として計上してしまった」といったミスもなくなるでしょう。
事業専用口座と会計ソフトを紐づけておけば帳簿付けもしやすいですし、経理作業の負担も減らせます。
融資が受けやすくなる可能性がある

個人事業主が屋号をつけると、融資が受けやすくなる可能性があります。これは屋号があることで「事業を営んでいる実態がある」と判断されやすいうえ、税務署で所定の手続き(開業届の提出、事業者としての確定申告など)をしている証明にもなることがその理由です。
もちろん、融資審査はその他の要素と合わせて総合的な判断がなされるため、屋号があるからといって必ずしも融資審査に通るわけではありません。しかしながら、個人名の場合と比べればやはり、屋号ありのほうが有利だといえるでしょう。
領収書・請求書・納品書などの書類に記載することができる
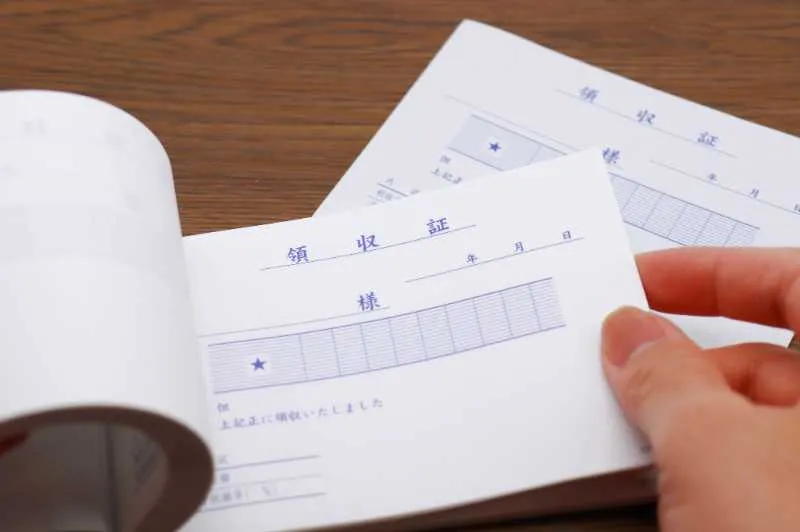
屋号は領収書や請求書、納品書といった証憑(しょうひょう)類にも記載ができます。個人名の領収書に比べると屋号入りの証憑書類は先方からの印象も良くなり、安心感を与えられるため信用の獲得にもつながりやすいでしょう。
特に相手が法人企業の場合、屋号があったほうが取引においての信用性も高くなり、次の取引につながるきっかけになる可能性が期待できます。
【領収書の屋号記載例】

【請求書の屋号記載例】

【納品書の屋号記載例】

クラウドソーシングなどの表示名に使用できる

クラウドソーシングサービスを利用する際、基本的には個人名で登録される方が多いのではないでしょうか?屋号を登録名にすれば、仕事を受注する側、さらに仕事を依頼する側のどちらにおいても信用性を高めることができます。
クラウドソーシングの受発注では実績が重視される傾向にありますが、顔の見えないサービスだからこそ信用性を少しでも高めたい……という方は、屋号での登録を検討してみてはいかがでしょうか。
名前の誤認・誤読を防ぐことができる

珍しい名前や難読苗字の方は、屋号をつけることで外部からの誤認や誤読を防ぐことができます。
たとえ相手方がこちらの名前を読めなくとも、屋号があれば「ショップ〇〇 ご担当者様」というふうに表記することができ、コミュニケーションコストを減らせます。スムーズなやりとりができれば、打ち合わせや交渉、契約などもスムーズに進みやすくなるでしょう。
また珍しい個人名の場合、外部から送られてくる宛名の記入間違いで郵便物や荷物の誤配につながることもあります。屋号を併記しておくとともに、屋号宛てで受け取りができるバーチャルオフィス(後述します)などを利用すれば、こうしたリスクを最小限に抑えられるでしょう。
バーチャルオフィスで郵便物の受け取りがスムーズになる

個人事業主の中にはバーチャルオフィスを利用していらっしゃる方も多いです。
特にご自宅でネットショップを運営されている方の中には、ネットに自宅住所を掲載することに抵抗があり、バーチャルオフィスを利用されるケースが多くみられます。
実はバーチャルオフィスの中には、屋号宛ての郵便物を受け取れるところもあります。
屋号が使えるバーチャルオフィスなら、個人名に加えて屋号宛てに届いた郵便物もまとめて保管してもらえますし、転送サービスを利用すれば自宅で受け取ることもできます。
「顧客や取引先が屋号宛てに郵便物を発送したが返送されてしまった」といったこともなく、受け取りがスムーズに行えるので大変便利です。
なおレゾナンスでは、バーチャルオフィスプランのご契約で屋号を無料登録していただくことができます(オプション利用で最大3つまでご登録可能)。ショップ名や事務所名のほか、YouTubeチャンネル名でもご登録可能です。
「屋号宛ての郵便物が多く届く」という方はもちろん、プライバシーを守りながらビジネスを行いたい方にも最適のバーチャルオフィスとなっています。
ご自宅でビジネスをされている方や、外での営業活動がメインで固定オフィスが必要ない方はぜひレゾナンスのご利用を検討してみてください。
\屋号宛ての郵便物が受け取れる!/
バーチャルオフィス|レゾナンス【月額990円〜】
個人事業主やフリーランスが屋号をつけるデメリットは?

結論から言えば、個人事業主やフリーランスが屋号をつけるデメリットはほぼありません。そもそも無料で登録できるうえ登録更新料などの費用もかからず、リスクがないからです。
ただ、人によっては次の2点がデメリットに感じることがあるかもしれません。
屋号を決めて登録する手間が生じる
屋号登録の手順としては「屋号を決めて、税務署へ登録の手続きを行う」というプロセスが必要です。
手続きそのものは書類を書いて提出するだけと簡単なのですが、
- 自身の事業に合った屋号か
- イメージの良い屋号か
- 同業者の屋号や商号、商標登録されている言葉等と重複しないか
といったことを考慮する必要があり、人によっては煩わしく感じる可能性があるでしょう。
対応業務が限定されてしまう場合がある
屋号の付け方によっては対応業務のイメージが固定化してしまい、受注できる仕事の幅が狭まる可能性があります。
例えばデザインもライティングもできる方が「〇〇ライティング」という屋号をつけた場合、外部からは「ライティング事業者」という印象を持たれやすくなります。
この場合、デザインの仕事の受注数が減り、WEBや書籍関連のライティング業務の仕事ばかりが来る可能性も考えられるでしょう。
複数のサービスを提供できる場合は「〇〇デザイン&ライティングLABO」のように提供価値がわかりやすい屋号をつけるか、販促ツール・WEBサイト等で提供できる価値をアピールするなどの対策を行いましょう。
屋号はあとからでもつけられる?

ここまでお読みになり、「屋号をつけないまま開業してしまったが、今からでもつけたほうがいいのでは?」と不安になった方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし結論から言えば、屋号は後からでも付けられますので、心配は要りません。
すでに開業している場合は確定申告で専用の欄に記入し、提出すればOKです。
今後の事業展開を拡大したいと考えているのであれば、屋号入り銀行口座の開設や融資など、屋号が必要になる場面も出てきます。また口座開設や融資などを利用しない場合でも、「事業のブランディングのため」などの理由で途中から屋号を付けたい場合もあるでしょう。
またすでに屋号を付けている方についても、所定の方法で変更ができます。
詳しくは次の項にて解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
屋号の提出方法と変更方法
屋号を登録する方法には「開業届に記入して提出する」「確定申告時に所定の欄に記入する」の2つがあります。
開業届で屋号を登録する方法
開業時に提出する「開業届」には屋号を記載する欄があります。
開業時点で屋号を決めている場合は、この欄に屋号を記入して提出すれば登録完了となります。

引用元:国税庁「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続」個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)
確定申告で屋号を登録する方法
屋号は確定申告の際に登録することもできます。
確定申告で登録するには、確定申告書内の「屋号・雅号」欄につけたい屋号を記入すればOKです。提出し受理された時点から、法的に屋号が登録されます。
開業時には屋号を決めておらず、後から屋号をつけたくなった場合はこの方法で登録申請するとよいでしょう。
青色申告を選択している場合は「所得税青色申告決算書」にも屋号を記入する欄がありますので、抜け漏れなく記載しておきましょう。
①【確定申告書(第一表)の屋号記載欄】

②【確定申告書(第二表)の屋号記載欄】

引用元:国税庁「確定申告書等の様式・手引き等(令和4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)」申告書第一表・第二表【令和4年分以降用】
③【所得税青色申告決算書の屋号記載欄】

引用元:所得税青色申告決算書(一般用)【令和5年分以降用】|国税庁
屋号を変更したいときは?
途中で屋号を変更したいとき、開業届を再提出する必要はありません。
確定申告を行う際に、確定申告書内の「屋号・雅号」欄へ、新たな屋号を記入すれば変更できます。
なお確定申告のタイミング以外で屋号を変更したい場合は、開業届を提出しなおすことでも屋号の変更が可能です。開業届の「その他記載事項」の欄へ「屋号を変更するため再提出」と記入しておきましょう。
なお、屋号変更後は取引先への通知を忘れずに行いましょう。また金融機関で屋号入りの銀行口座を保有している場合は、変更の届出が必要になります。こちらも忘れずに手続きを済ませておきましょう。
いい屋号のつけ方・決め方のポイント

ここからは、“いい屋号”のつけ方のポイントを解説します。
いい屋号とは「見た(聞いた)だけでどんな事業なのかがわかりやすい」「本人のサイト等にアクセスしやすい」といった要素を含む名称を指します。これら要素を含む屋号はビジネスの発展・成功にもつながりやすく、個人事業をより充実させたい方はぜひ意識すべきです。
いい屋号をつけるためにも、3つのポイントをチェックしてみましょう。
【▼屋号付けのルールや注意点についてもっと知りたい方はこちら】

事業内容を思い浮かべやすい屋号にする
個人事業主が屋号をつける際には「どんな事業をしているのか、どのような専門性があるのか」を思い浮かべやすい名称にしましょう。
よくあるのが「ショップ○○」や「○○サロン」「○○事務所」といった屋号ですが、それだけでは具体的にどんなお店・サロン・事務所なのかがわかりにくいですよね。
一方、「アクセサリーショップ○○」「脱毛サロン○○」「○○司法書士事務所」といった屋号であればどうでしょうか?
これらのような具体性の高い屋号であれば、ぱっと見たり聞いたりしただけで事業内容をイメージしやすくなります。
ビジネスを有利に進めていくためにも、屋号付けの際には必ず具体的な事業名を盛り込みましょう。
ドメインを取得するときのことも考えておく
個人事業用のWEBサイトを開設したい場合は、ドメインが取得できる屋号を心がけることも大切です。
ドメインとはWEBサイトのURLのうち「http://www.○○.co.jp」の○○にあたる部分のことです。ビジネスではお金を払って「独自ドメイン」を取得し、サイトを運用したりメールアドレスに使ったりする場合が一般的ですが、屋号をこのドメインに入れることで顧客に覚えてもらいやすくなります。
なお、現在すでにほかの人が使っているドメインは使用できません。屋号をドメインにしたい場合は、その屋号がすでにドメインとして使われていないかもチェックしておくとよいでしょう。
検索されやすいワードにする
近年はどの業態もインターネットやSNSから集客をする方法が一般的となっています。そのため、屋号をつける際には「ウェブ検索やSNS内の検索で引っ掛かりやすいワード」を盛り込むとよいでしょう。
具体的にいうと、ウェブ検索では「地域名+業種」で検索されるケースが多いので、地名や業種を盛り込んだ「港区○○オーガニックストア」のような屋号がベストです。
検索にヒットしやすいワードを盛り込むことでWEBサイト等が上位に表示されやすくなり、集客効果を高められる可能性があります。
個人事業主・フリーランスが屋号をつけるときの注意点

屋号付けにはそこまで厳しいルールはありません。
ただし、今後法人化を検討している場合は、文字や記号の使用に一定の制限が求められるケースもあります。また他の事業者と混同しやすい屋号や商標登録されている野合、覚えにくい屋号も避けるべきです。
以下では、屋号付けの注意点について詳しく解説します。
法人化する場合は屋号に“会社名に使えない記号”を使わないよう注意
起業された方の中には「最初は個人事業として始めて、ゆくゆくは法人化を目指したい」という方もいらっしゃるかと思います。その場合は「!」「?」「@」などの会社名に使えない記号が入った屋号を避けたほうがよいでしょう。
屋号では漢字・ひらがな・カタカナ・アルファベットのほか、記号やアラビア数字なども使用できます。記号に関しては「!」「?」「☆」など幅広く使用でき、特に制限もありません。
しかし、会社名(商号)は屋号のように幅広い種類の記号を使用することができません。
会社名(商号)として公式に法的に使用が許可されている記号は以下の6種類であり、それ以外ではローマ字を使って複数の単語を使う場合の区切りとして空白(スペース)の利用が許可されているのみとなっています。
【会社名(商号)に利用できる記号】
| 記号 | 読み方 |
|---|---|
| & | アンパサンド |
| ’ | アポストロフィー |
| , | コンマ |
| ‐ | ハイフン |
| . | ピリオド |
| ・ | 中点 |
個人事業である程度実績を積んでから法人化する際、これまでの屋号を捨てて別の名称を会社名にしてしまうと何かと不便ですし、周知・連絡などの手間もかかります。
法人化を見据えているのであれば、最初からそのまま会社名にできる屋号をつけておきましょう。
他の事業者と間違えやすいものは避ける
屋号をつける際には、他の事業者(個人・法人問わず)との混同を招く屋号を避けましょう。
同じ地域で似たような屋号の事業者や会社がある場合、混同を招いてトラブルに発展したり、最悪の場合は訴訟に発展したりといった可能性もあるからです。そうなれば事業にとっても大きなイメージダウンになります。
加えて、屋号をつける際は商標登録されている商品・サービス、すでにかなりの知名度がある名称なども避けたほうが無難です。
つけたい屋号の候補を考えたら、必ずGoogleなどの検索エンジンや国税庁法人番号公表サイト(法人登記をした会社の商号を調べられるサイト)、特許情報プラットフォーム(商標登録された名称を検索可能)などで重複していないかを確認しましょう。
参考リンク:
国税庁法人番号公表サイト(会社名・商号の検索が可能)
特許情報プラットフォーム|J-PlatPat [JPP](商標登録された名称を検索可能)
覚えにくい屋号を避ける
屋号は使える文字の種類も多く、長さについても特に規定はありません。ただし、あまりに長く覚えにくいもの、ほとんどなじみのない名称などをつけてしまうと、見た人が覚えにくくなってしまう点に注意が必要です。
逆に言えば、ビジネスのチャンスを増やしたいなら覚えやすい屋号にすべきです。覚えやすい屋号は人々の印象に残りやすく、顧客側からしてもWEB検索や問い合わせが気軽に行えますので、商品やサービスの購入・利用に繋がりやすくなります。
【覚えやすい屋号の例】
| 馴染みのある単語を使った屋号 | おむすび屋〇〇 花と緑の〇〇 など |
|---|---|
| 敬称をつけて擬人化した屋号 | 家事代行〇〇さん オーダースーツ Mr.〇〇 など |
せっかく屋号をつけるのなら、ぜひ「初見で覚えられる屋号」を目指してみましょう。
屋号をつける際によくある質問(Q&A)

Q1.個人事業主やフリーランスは屋号をつけたほうがいい?
A. 屋号は義務ではなく、屋号なしでも法的な問題はありません。ただし屋号をつけることで、ビジネスの信頼性が向上し、顧客や取引先に事業内容を明確に伝えることができます。
また屋号入りの銀行口座を開設したり、融資を受けやすくなったりする場合もあるため、ビジネスを大きくしたい場合は屋号をつけることを推奨します。
Q2.屋号はあとからでもつけられる?
A.屋号は開業後でも追加・変更が可能です。開業届や確定申告時に登録でき、手続きも複雑ではありません。
事業が発展した段階で屋号を付けたり、再ブランディングの一環として変更することもできます。
途中で屋号を変更した場合は、金融機関や取引先への通知も忘れずに行いましょう。
Q3.屋号をつけることで得られるメリットは?
A. 屋号をつけると事業の名称・内容が顧客にわかりやすく伝わり、認知度や信頼性が向上します。
また名刺や請求書、クラウドソーシングのプロフィールページなどに屋号を記載することでプロフェッショナルな印象を与え、営業面でも有利になります。
屋号入りの事業用銀行口座を持てば事業用資金とプライベートのお金を分けられ、管理しやすくなるメリットもあります。
Q4.屋号の変更に必要な手続きは?簡単にできる?
A. 屋号の変更は税務署に開業届を再提出し、銀行口座の名義変更や取引先への通知を行えばOKです。
変更自体はとても簡単な手続きのみで済みますが、新しい屋号が事業の成長やブランディングに適しているかを十分検討し、変更後もスムーズにビジネスが進むよう準備をしてから変更するとよいでしょう。
Q5. 屋号なしで事業を行うリスクはある?
A. 屋号なしでも事業は運営可能ですが、取引先や顧客からの信用が低く見られることがあります。また、金融機関での口座開設や融資申請ができないケースも多いです。
屋号を持つことで事業の認知度を高め、営業活動をスムーズに進められるため、外部の事業者や法人企業との取引が多い業種の方は屋号をつけることをおすすめします。
レゾナンスのバーチャルオフィスは“屋号宛て”の郵便物も転送OK!

本記事では屋号をつけるメリット・デメリットや、後から屋号をつける方法をお伝えしました。
バーチャルオフィスを利用して個人事業を行う場合、提供業者によっては「契約者の氏名宛て」の郵便物の受け取りには対応していても、屋号宛ての郵便物には対応していないケースが多く見られます。
レゾナンスでは、屋号宛てに届いた郵便物でもお受け取り・転送をいたします。
そのため、屋号を活用してビジネスを展開したい個人事業主様でも、安心してご利用いただけます。
- 契約プラン1つにつき屋号1つまで無料で登録可!
- 屋号での郵便物お受け取りに対応可
- YouTubeチャンネルのチャンネル名でも登録OK!
- オプションで屋号を追加OK(最大3つまで登録可)
- 到着した郵便物、お荷物はお写真で確認可能
- 月額990円からの格安で都心一等地の住所がご利用いただけます!
【レゾナンス 屋号登録料金の一覧表】
| プラン名 | 屋号登録料 | 屋号2つ目以降の追加オプション料金 |
|---|---|---|
| 月1転送プラン (基本料金990円/月〜)※ |
屋号1つまでは無料で登録可 (追加料金なし) |
+990円/月 (最大3つまで登録可) |
| 週1転送プラン (基本料金1,650円/月〜)※ |
屋号1つまでは無料で登録可 (追加料金なし) |
+1,650円/月 (最大3つまで登録可) |
※年払いの場合の料金となります
レゾナンスでは個人事業主の会員様の約半数が屋号をご登録中!
郵便物やお荷物のお受け取りにご活用されています。
ビジネスの信頼感を高めるには、屋号の活用がおすすめです。
バーチャルオフィスのご利用をお考えの個人事業主様は、ぜひ屋号が使えるレゾナンスのバーチャルオフィスをご検討ください!
▼レゾナンス・バーチャルオフィスの料金&サービスについてはこちら
▼どのプランがおすすめ?バーチャルオフィスプラン診断はこちら