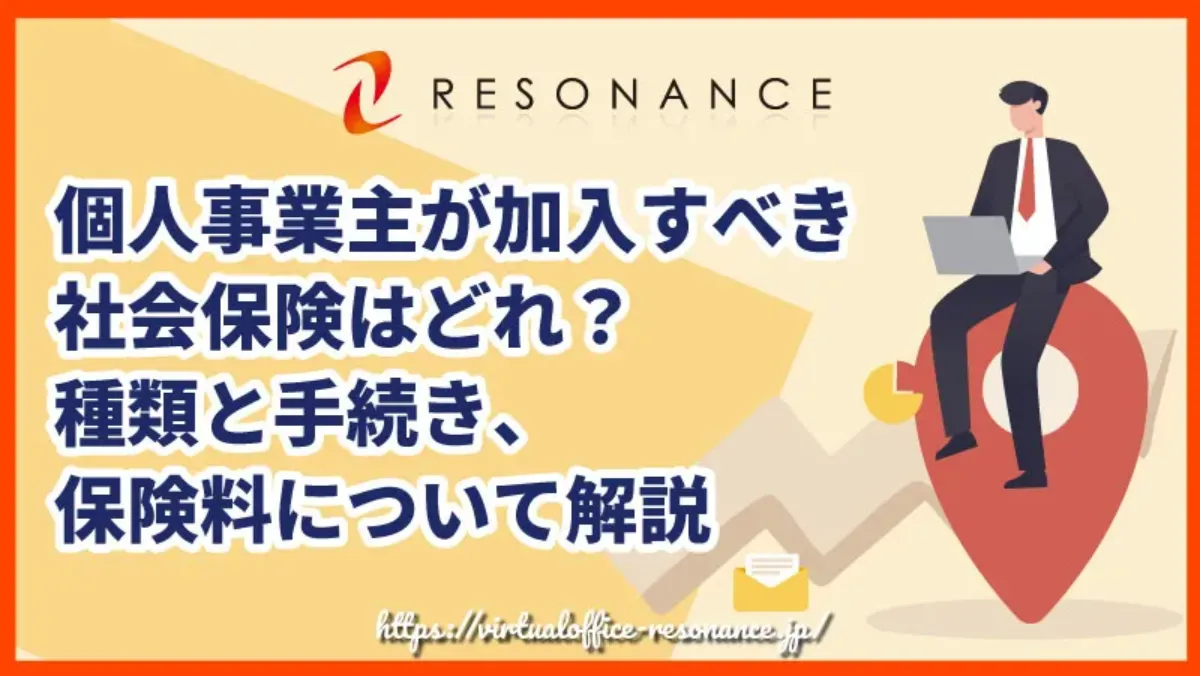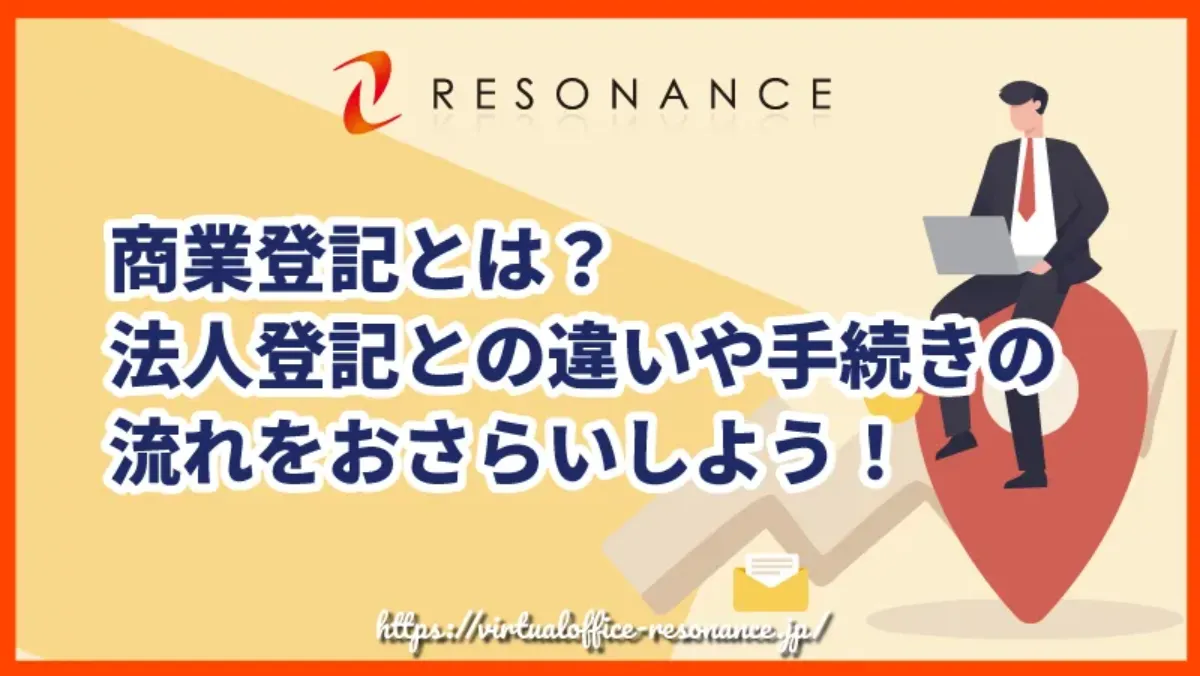個人事業主として独立したとき、考えなければならないのが「社会保険」についてです。
会社員の場合、健康保険組合などの健康保険、厚生年金や雇用保険、労災保険などに加入しますが、個人事業主は国民健康保険・国民年金といった保険に加入することになります。
とりわけ国民健康保険については病気や怪我など病院へかかる際に重要なものですが、これらは会社員の社会保険とどのような違いがあるのでしょうか?
本記事では個人事業主が加入すべき社会保険について解説。
会社員と個人事業主の場合の違いや、国民健康保険についての知識、任意継続の方法などをご紹介します。さらには、個人事業主が加入できる国民健康保険組合や扶養家族として社会保険に加入する条件、確定申告についてもご説明しています。
これから個人事業主として開業される方は、ぜひご参考にしてみて下さい。
個人事業主になったら社会保険はどうする

日本では「国民皆保険」という義務があります。これは、日本に住む人は原則として全員が社会保険(会社の健康保険)か国民健康保険へ加入しなくてはならないというものです。
個人事業主は、原則として「国民健康保険」へ加入することになります。
■医療保険制度の体系
| 国民健康保険 | 個人事業主や無職、年金生活者が加入する保険 |
|---|---|
| 健康保険 | 民間会社の会社員が加入する保険 |
| 共済組合 | 国家公務員、地方公務員、私学の教職員が加入する保険 |
| 船員保険 | 船員として船舶所有者に使用される人が加入する保険 |
| 後期高齢者医療制度 | 75歳以上の方および65歳~74歳で一定の障害の状態にあることにつき後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人が加入する保険 |
参考リンク:医療保険制度の体系 | こんな時に健保 | 全国健康保険協会
以下では会社員と個人事業主の社会保険の違い、個人事業主が加入できる社会保険の種類について解説します。
個人事業主と会社員による社会保険の違い
個人事業主が加入する健康保険は「国民健康保険」です。
一方会社員は、健康保険組合等の健康保険へ加入します。会社員の健康保険は厚生年金・雇用保険・労災保険と合わせて「社会保険」とひとまとめに呼ばれる場合が多いです。
| 個人事業主 | 会社員 | |
|---|---|---|
| 保険の種類 | 国民健康保険 | 健康保険組合、協会の保険 (社会保険) |
| 保険料の負担割合 | 全額自己負担 | 会社と折半 (半額負担) |
| 保険料の算出方法 | 前年所得から算出 (世帯人数に応じて増額あり) |
一定の期間の給与・賞与等の平均額から算出 (扶養人数に応じた増減なし) |
| 医療費負担 | 3割負担 | 3割負担 |
| 出産手当・傷病手当の有無 | なし | あり |
| 支払い方法 | 自ら支払いが必要 | 給与天引き |
医療費の窓口負担はどちらも3割で同じですが、国民健康保険は会社員の社会保険と異なり、全額自己負担となります。また世帯全員分の保険料がかかるため、世帯人数が多くなるほど支払額も多くなります(未就学児等は減額措置があります)。
加えて、会社員の場合は出産手当金や傷病手当金がもらえますが、国民健康保険はどちらもありません。支払い方法も天引きではなくなるため、支払い忘れ・支払い漏れに注意する必要があります。
個人事業主が加入できる保険の種類について
個人事業主が加入できる健康保険については、以下の4種類があります。
- 国民健康保険
- 会社の健康保険組合の任意継続
- 民間団体の国民健康保険組合
- 家族の社会保険(扶養認定を受けて加入)
中には申請期限や加入条件が定められているものもあります。
たとえば任意継続をしたい場合は、退職日の翌日から20日以内に手続きをする必要があります。また家族の社会保険の扶養に入りたい場合、扶養認定を受けるにあたって所得上限があるケースも珍しくありません。
個人事業主が国民健康保険に加入する場合

ここからは、個人事業主が国民健康保険に加入する際の手続きの流れや、保険料の算出方法について解説します。
国民健康保険の加入は自治体窓口での手続きが原則となりますので、以下を把握した上で必要書類を抜け漏れなく準備しましょう。
手続きの流れ
個人事業主が国民健康保険の加入手続きをする際の流れは以下のとおりです。
退職日の翌日から14日以内に手続きを行う必要がありますので注意しましょう。
※扶養家族がいる場合は少し流れが異なります。
【国民健康保険へ加入する流れ】
- 必要書類を揃える
- 健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失確認通知書
- 本人確認書類(運転免許証やパスポート、マイナンバーカード等)
- マイナンバーが確認できる書類
- 銀行等のキャッシュカード
- 自治体の窓口へ必要書類を提出する
- 国民健康保険証を受け取る
手続きの際にはまとめて国民年金の加入も行うとよいでしょう。
自治体によっては必要書類が追加で必要になる可能性もあるため、あらかじめ問い合わせておくと手続きがスムーズです。
国民健康保険料の算出方法
国民健康保険料の保険料は「平等割」「均等割」「所得割」の3つの要素を合わせて構成されています。保険料は自治体ごとに定められており、自治体によっては資産割が加算される場合もあるため、あらかじめ確認されることをおすすめいたします。
| ①平等割 | 一世帯に対し定額でかかる部分 |
|---|---|
| ②均等割 | 世帯全体の国民健康保険の加入者数 均等割額 × 加入者数 = 均等割 |
| ③所得割 | 前年総所得金額 – 43万円 × 所得割額 = 所得割 |
また、40〜64歳の加入者は介護保険料を上乗せで支払うことになります。
詳しい保険料は管轄の自治体ホームページを確認してみましょう。
参考リンク:保険料額について|東京都保健医療局
個人事業主が健康保険組合を任意継続する場合

個人事業主になる前に会社などで健康保険組合に加入していた場合、任意継続をする方法もあります。
任意継続をするメリットは、家族を扶養に入れたままにできるため世帯全体の保険料が抑えやすい点、組合独自の福利厚生が利用できる点です。
ただし、保険料が労使折半ではなく100%個人負担になる点には注意が必要です。
ここでは個人事業主が健康保険を任意継続する場合の手続きや保険料、継続期間について解説します。
手続きの流れ
個人事業主が会社の健康保険を任意継続するには、退職日の翌日から20日以内に健康保険組合へ申請しなくてはなりません。
任意継続には要件がありますので、自身が要件に適合しているかをチェックした後、「任意継続被保険者資格取得申出書」を取得し、居住地管轄の組合・協会へ提出します。
①任意継続の要件について確認
②任意継続被保険者資格取得申出書を取得、記入
(家族を被扶養者として手続きする場合は被扶養者届の提出も必要)
③ ②と添付書類を居住地管轄の組合・協会へ提出
④任意継続
健康保険組合によっては「資格喪失日の前日(最終在籍日)までに「継続して2ヵ月以上の被保険者期間」があること」などの要件を設けている場合もあるため、かならず細部まで確認しておきましょう。
また扶養家族がいる場合は、被扶養者届に加えて「課税証明書」「住民票の写し」などの証明書類の提出が求められますので、あらかじめ必要書類を確認して揃えておきましょう。
保険料と継続期間について
任意継続する場合の保険料は保険料率によって変わりますが、その保険料率はお住まいの地域、扶養家族の有無によって異なります。保険料は全額自己負担となり、原則2年間同一額となります。
また保険料は退職時の標準報酬月額を基準に算定されますが、多くの健康保険組合では「退職時の標準報酬月額が30万円を超えていた場合、一律で30万円の標準報酬月額により算出した保険料が適用される」などの規定を設けています。
なお、継続期間は2年を上限としており、2年経過後は「任意継続被保険者資格喪失通知書」が送付され、被保険者資格を失います。このとき、国民健康保険などへの加入が必要になる点も押さえておきましょう。
個人事業主が各団体の国民健康保険組合に加入する場合

個人事業主が健康保険へ加入する方法には、国の健康保険だけでなく一般の団体が運営する「国民健康保険組合」へ加入する方法もあります。
国民健康保険組合はおもに自営業やフリーランスなどの個人事業主を対象とした団体で、加入者の所得額によっては国の国民健康保険へ加入するよりも保険料が抑えられる可能性があります。
ここでは、クリエイター向け・美容業向けや地方自治体の国民健康保険組合についてご紹介します。
文芸美術国民健康保険組合に加入する方法と保険料
文芸美術国民健康保険は、法人化していない個人事業主で、文芸や美術、著作業などに従事しているクリエイターを対象とした国民健康保険組合です。
加入するには「ジャパン デザイン プロデューサーズ ユニオン」「日本広告写真家協会」など、組合を構成する団体のいずれかへ加入することが条件となります。(加入団体一覧/P4)
保険料が所得にかかわらず一律の金額のため、所得が高い方ほどメリットが大きいです。
ただし、加入する団体によっては入会費・年会費等が必要になる場合があるため、必ず事前に確認しておきましょう。
【文芸美術国民健康保険組合の保険料(月額)】
| 医療保険 後期高齢者支援金分 |
組合員 | 1人につき月額25,700円 (医療保険分19,900円、後期高齢者支援金分5,800円) |
|---|---|---|
| 家族 | 1人につき月額15,400円 (医療保険分9,600円、後期高齢者支援金分5,800円) |
|
| 介護保険分 (満40〜64歳までの被保険者) |
1人につき月額5,700円 | |
| 特例組合員分 (満75歳までの組合員) |
1人につき月額1,000円 | |
出典元:文芸美術国民健康保険組合(2024年7月時点の掲載情報)
なお、家庭に未就学児被保険者がいる場合は1人につき年額12,000円の軽減措置が受けられます。
また産前産後被保険者については、1人なら4ヶ月、2人以上では6ヶ月の軽減措置が受けられます。
東京美容国民健康保険組合に加入する方法と保険料
東京美容国民健康保険組合は、東京都内の事業所で美容業に従事している事業者で、かつ近隣県に居住している人(神奈川・千葉・埼玉・茨城・山梨県)が対象の国民健康保険組合です。
個人事業主はもちろん、法人でも加入でき、保険料は所得に関わらず一律となっています。
申し込みには所定の申請書・健康保険加入状況確認書のほか、保健所発行の開設届け済み確認書のコピーや前年度の確定申告書のコピー、世帯全員のマイナンバー入り住民票、被保険者証または資格喪失証明書のコピーが必要です。
【一般被保険者の保険料】
| 事業主組合員 | 1人につき月額20,000円(均等制) |
|---|---|
| ●従業員組合員 | 1人につき月額14,500円(均等制) |
| ●同一世帯家族 | 1人につき月額9,500円 (人頭割~組合員・世帯主負担) |
| ●同一世帯家族(未就学児) ※義務教育就学前 |
1人につき月額6,000円 (人頭割~組合員・世帯主負担) |
【介護納付金賦課被保険者(40歳~64歳)の保険料】
| 事業主組合員 | 1人につき月額23,000円(均等制) |
|---|---|
| ●従業員組合員 | 1人につき月額17,500円(均等制) |
| ●同一世帯家族 | 1人につき月額12,500円 (人頭割~組合員・世帯主負担) |
出典元:東京美容国民健康保険組合(令和6年4月からの保険料)
地方自治体ごとの国民健康保険組合に加入する方法と保険料
さきほどご紹介した2例以外にも、地方自治体や職種・業種ごとの国民健康保険組合があり、条件を満たせば加入することができます。
- 東京都医師国民健康保険組合:東京都で医療・福祉業に従事する方が加入できる
- 東京建設職能国民健康保険組合:(社)東京建設職能組合連合会に加入している組合員とその家族が加入できる
- 東京食品販売国民健康保険組合:食品業に従事し、店舗が東京都内にある個人事業主と従業員およびその家族が加入可能
このほかの国民健康保険組合については全国国民健康保険組合協会の公式サイトから調べられるほか、開業している場所の自治体名と国民健康保険組合で検索をしてみると、さまざまな情報が確認できます。
加入条件や保険料は団体ごとに異なりますので、あらかじめ確認した上で加入をご検討ください。
個人事業主が扶養家族として社会保険に加入する場合

個人事業主の社会保険については、ご家族(配偶者や親など)の扶養家族として社会保険に加入する方法もあります。多くの健康保険組合では、所得などの条件を満たしさえすれば、個人事業主として開業されている方(白色・青色申告)でも扶養に入ることができます。
ただし、扶養認定の条件は健康保険組合によっても変わってくるため、必ずしも加入できるとは限りません。扶養認定を受けられない場合は、ご自身で国民健康保険・国民年金に加入する必要がありますので注意しましょう。
個人事業主の社会保険と確定申告について
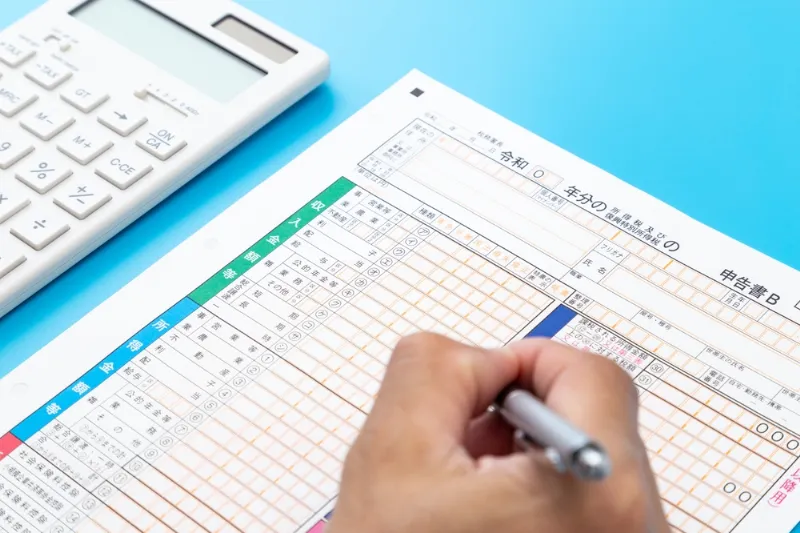
個人事業主が支払った社会保険料については、確定申告で控除(社会保険料控除)が受けられます。
社会保険料の申告をしなくとも罰則などはありませんが、確定申告をした場合は申告した金額を課税所得から全額控除できるため、所得税・住民税額の節税につながります。毎年の確定申告では、社会保険料を忘れずに申告しましょう。
なお、控除の対象となる保険料は以下のとおりです。
| 保険料の種類 | 確定申告時のポイント |
|---|---|
| 国民健康保険料 | 自身で1年間の納付額を計算し、確定申告書に記載する |
| 国民年金保険料 | ・「社会保険料控除証明書」に記載されている納付額を確定申告書に記載する ・証明書は毎年11月ごろに届くので、確定申告書に添付し、提出する |
| 労働保険料 (労災保険+雇用保険料) |
給付基礎日額によって金額が変わる |
| 家族(配偶者など)の社会保険料 | 家族が自分の社会保険料を社会保険料控除に含めていない場合、申告者自身の控除が受けられる |
| 介護保険料 | ・自身が支払った範囲に限り社会保険料控除に含められる ・支払った際の領収書や介護保険料納付済額通知書の添付書類が必要 |
なお、従業員の社会保険料を個人事業主が負担した場合は、福利厚生費として経費計上をします。
社会保険料に含めて申告しないよう注意しましょう。
個人事業主様には、低コストで開業用のビジネス住所が使える「バーチャルオフィス」がおすすめ!ゼニスのバーチャルオフィス「レゾナンス」なら、月額990円(ネットショップなら550円)がご利用可能。都心一等地、ブランド力の高い住所でビジネスを始めてみませんか?
詳しく見る
まとめ
本記事では個人事業主の社会保険について解説してまいりました。
個人事業主になると国民健康保険や国民年金といった保険に加入することになります。
これらの加入条件や保険料は会社員向けの社会保険と大きく異なるうえ、所得によっては個人事業主でも加入できる健康保険組合を利用した方が支出を抑えられるケースもあります。
健康保険については、ご自身の所得や業種、状況に応じた健康保険を探されたり、任意継続やご家族の扶養に入ったりといった選択肢を検討されるとよいでしょう。
また、確定申告の際には社会保険料を正しく申告し、控除を受けることも忘れずに行いましょう。