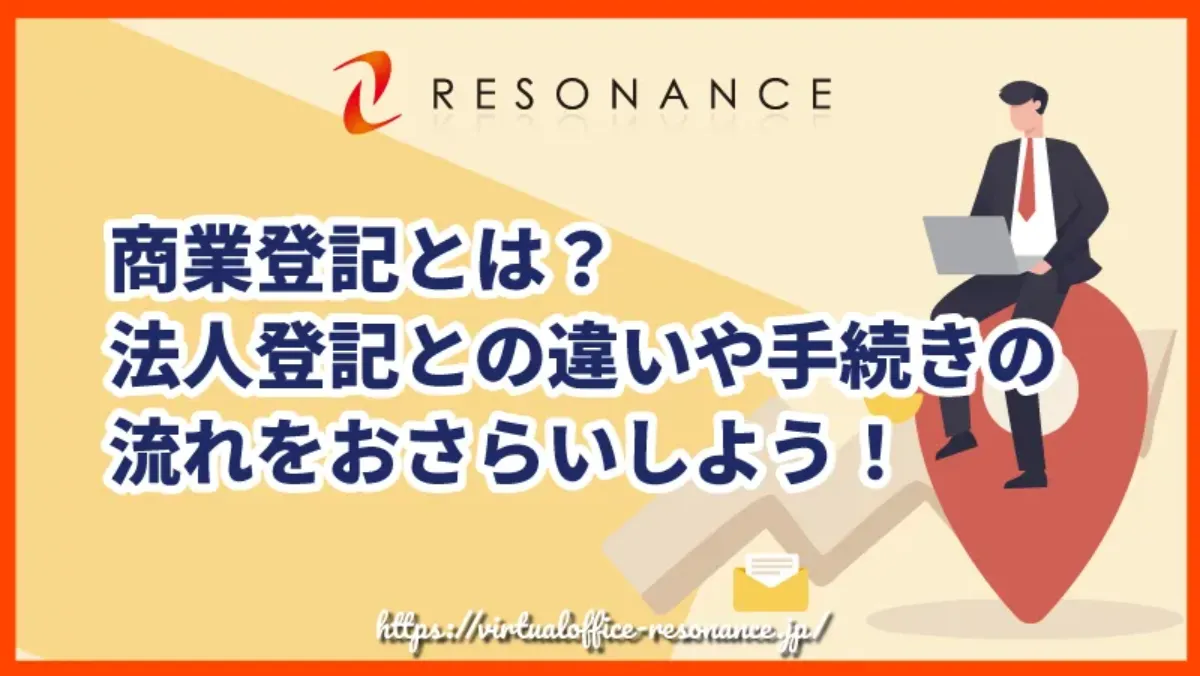会社員の副業が人気ですが、「いくらぐらい稼ぐと確定申告が必要になるの?」と疑問に思う方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、会社員の副業で確定申告が必要になる“ボーダーライン”や、経費の扱いを解説。確定申告をしなかった場合の罰則、住民税に関する注意点や、確定申告の種類についてもご紹介します。
会社員で副業を検討している方や、副業を始めたばかりの方はぜひチェックしてみてくださいね。
会社員の副業では「年間収入20万」から確定申告が必要!
会社員が副業をした場合、年末調整とは別に自分で確定申告をしなければならないケースがあります。
具体的には、年間の副業収入が「20万円」を超えた場合、会社員でも確定申告が必要になります。
俗にいう「20万円ルール」と呼ばれる決まりです。
ただしこの20万円は、給与収入(アルバイトなど雇われて稼いだお金)か、それ以外かによって意味合いが異なります。
- アルバイトの場合:給与収入が20万円を超えたら、確定申告が必要
- それ以外の場合(業務委託など):課税所得が20万円を超えたら確定申告が必要
給与収入や課税所得が20万円に満たない場合は、確定申告をする必要はありません。
会社員で確定申告が必要となるケースについて、国税庁のホームページには以下のように記載されています。
会社員で確定申告が必要となるケース
給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人(確定申告をすれば税金が還付される人は除きます。)は、確定申告をしなければなりません。(1) 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
(2) 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(3) 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人注:給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
(4) 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
(5) 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
(6) 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
(7) 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人参照)国税庁(No.1900「 給与所得者で確定申告が必要な人」)
上記の中で副業に関する項目は、(2)と(3)です。
(2)は、副業が給与所得ではないケース、(3)は、副業も給与所得のケースです。
それぞれについて、詳しく見てきましょう。
副業が給与所得のケース
アルバイトやパートなど、副業の収入を給与として収入を得ている場合は、給与所得となります。
2か所以上の事業所のうち、メイン収入となる給与以外に得る給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要だとされています。
なお、副業が給与所得の場合は、経費計上ができない代わりに、収入金額に応じた給与所得控除が適用されます。
副業による収入が20万円以下の場合においても、副業を含めた給与収入の合計額から、所得控除(雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外)を差し引いた金額が150万円超の場合は、確定申告が必要となるので注意しましょう。
給与所得 = 給与(収入) – 給与所得控除
本業の事業所と同様、副業先の事業所からも源泉徴収票が出ますので、確定申告では、本業だけでなく副業も含めた両方の源泉徴収票を揃えましょう。
本業の勤務先で年末調整を受けるために、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。
扶養控除等(異動)申告書を提出できるのは、1事業所に限られるため、一般的には所得額の多い本業の勤務先にて年末調整を行います。
本業の会社で年末調整を受けたうえで、副業の所得に対しては自分で確定申告を行うことで、本業と副業の給与所得を合算し所得税を再計算します。
確定申告の申告書は、確定申告書A(給与所得者用の申告書)を使います。
もし、副業の勤務先でも扶養控除等(異動)申告書を提出してしまい、本業と副業の両方で源泉徴収が行われてしまった場合は、所得税の控除額が誤って計算されている可能性がありますので、確定申告を行って正しい金額に修正するようにしましょう。
副業が給与所得でないケース
副業が給与所得でなく、事業所得や雑所得などにあたる場合は、副業の収入から副業に必要となった経費を引いた金額が20万円を超えた場合に、確定申告が必要となります。
事業所得(または雑所得)= 収入 – 経費
経費とは、事業を行うために必要となった費用で、仕事中の移動交通費や書籍・事務用品代、光熱・通信費などが該当します。
本業からの給与収入に関する源泉徴収票と、副業で得た収入金額をもとに、確定申告を行います。経費に計上した支出のレシートや領収書は、捨てずに一定期間保管するようにしましょう。
副業が原稿料やフリマやオークション出品によって得た収入、アフィリエイトによる収入であれば、「雑所得」となります。また、FXや仮想通貨取引による利益も雑所得となります。
雑所得の規模が大きくなり継続的に収入を得る場合は、事業所得して青色申告が利用できます。青色申告では所得税の控除によるメリットが大きくなるケースも多いでしょう。
株取引やサラリーマン大家の場合
株取引を副業としている場合で、株取引で収入を得たという場合は、確定申告では譲渡所得として申告します。ただし、取引で使っている口座によっては、確定申告が不要な場合もあり、「源泉徴収ありの特定口座」や「NISA口座」では確定申告の必要がありません。
一般口座や「源泉徴収なしの特定口座」の場合で、利益が20万円を超える場合については、確定申告をする必要があるので、ご自身の口座がどちらにあたるのかを確認するようにしましょう。
また、会社員として働きながらアパートの家賃などの不動産収入を得るサラリーマン大家さんと言われる人もいるでしょう。この場合の所得は不動産所得となり、家賃などの収入から経費を引いた額を所得として計算します。建物には減価償却があり年々価値が減る分についても減価償却費として経費とすることができます。
会社員の副業ではどんなものが経費になる?
会社員がアルバイト以外で副業収入を得た場合、「雑所得」として確定申告を行うのが一般的です。
その際、副業に使った「経費額」を申告できますので、忘れずに行いましょう。
経費を差し引けば課税所得額が少なくなるため、節税につながります。
- 家賃、光熱費※
- 通信費(インターネット料金、スマホ料金など)※
- 販売商品の仕入れ費、材料費(売上原価)
- 消耗品費(事務用品、10万円未満の備品)
- 広告宣伝費(チラシやWeb広告など)
- 販売促進費
- 外注費(仕事を外注した費用)
- 交通費(取材などに費やした電車代など)
※固定費については副業で使用した分を「家事按分」する必要があります。
また白色申告の場合、経費計上するには「業務利用割合が50%以上」などの規定をクリアしなくてはならないため要注意です。
経費計上する場合、経費の領収書やレシート、クレジットカードの支払い明細を保管する必要があります。
保管期間は5年間となりますので、必ず保管しておきましょう。
会社員の副業では「住民税」の申告漏れに要注意
会社員の副業において「20万円ルール」が適用されるのは、あくまでも「所得税」に関する確定申告のみです。
住民税については「20万円ルール」が無いため、お住まいの市区町村へ申告しないと「申告漏れ」になってしまいます。
【住民税の申告方法】
住民税の申告先は、お住いの市区町村の役所です。毎年3月ごろ、確定申告と同じ時期に申告をします。
会社員の本業分+副業の所得を申告したあと、以下の5つを合わせた「住民税」が計算されます。
- 所得割
- 均等割
- 利子割
- 配当割
- 株式等譲渡所得割
副業がアルバイト以外なら「普通徴収」にするのがおすすめ
住民税の納付方法には、給与から天引きされる「特別徴収」と、払い込み用紙などで納付をする「普通徴収」があります。
会社員の場合、何も選ばなければ「特別徴収」として毎月天引きされます。しかし会社に副業のことを話していない場合は注意が必要です。
副業により住民税額が増えると、「給与は上がっていないのに住民税だけ増えている」と怪しまれ、会社に副業がばれてしまう可能性があるからです。
一方普通徴収を選んだ場合は、給与からの天引きではなく「払い込み用紙」を使って自分で支払うことになります。この場合、住民税が増えても会社に知られることはありません。
- 副業がアルバイトなどではなく、業務委託などで所得を得ている
- 会社に副業のことをばらしたくない
これらの条件に当てはまる副業会社員は、普通徴収を選ぶとよいでしょう。
ちなみに、会社員の副業が「アルバイト・パート」の場合は、原則として特別徴収が適用されます。
副業で20万円以上稼いだ会社員が確定申告しないとどうなる?

会社員が副業で20万円以上稼いで確定申告の対象になっているにもかかわらず、申告をしない場合はどうなるのでしょうか。
実際に未申告のまま放置した場合、以下の罰則が課せられます。
- 「無申告加算税」が課せられてしまう
- 悪質な場合は「重加算税」が課せられる場合も
- 納税を延滞した場合は「延滞税」がかかる
「無申告加算税」が課せられてしまう
会社員の副業で確定申告対象であるのに申告をしていない場合、無申告加算税が課せられます。
納付すべき税額が50万円までの場合は15%、50万円を超える部分は20%が上乗せされる仕組みです。
ただし、税務署の調査が入る前に確定申告をすれば、無申告加算税が軽減されることがあります。
確定申告の対象になった場合は、忘れずに申告を行いましょう。
悪質な場合は「重加算税」が課せられる場合も
会社員の副業で確定申告対象なのに申告をせず、かつ内容が悪質(帳簿の改ざんや二重帳簿など)な場合は「重加算税」が課せられることがあります。こちらは追加本税の35~40%と、重い処分となります。
納税を延滞した場合は「延滞税」がかかる
税金が課せられているのに期限内に納めなかった場合は、延滞税が課せられます。
延滞税は法定納期限の翌日~納付日までの期間、滞納額によっても変わります。
参考:延滞税の計算方法|国税庁
白色申告と青色申告の違い!会社員の副業におすすめなのは?
会社員の副業で確定申告をする場合は「白色申告」「青色申告」のどちらかを選ぶことになります。
白色申告は特に事前申請など必要ありません。一方、青色申告をする場合は、「開業届」「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
それぞれのメリット・デメリットを見てみましょう。
| 白色申告 | 青色申告(65万円控除の場合) | |
|---|---|---|
| 事前の申し込み | 不要 | 以下の書類を提出する必要あり
※その年の3/15までに要提出。 |
| 所得からの控除額 | 基礎控除48万円 (所得2400万円以下の場合) |
e-Taxで確定申告をした場合
合計113万円 ※郵送、税務署での確定申告では特別控除額が55万円となります。 |
| 帳簿の付け方 | 単式簿記 | 複式簿記 |
| 保存帳簿、書類 |
|
|
| メリット |
|
|
| デメリット |
|
|
※青色申告には、単式簿記で申告できる方式(10万円控除)もあります。
帳簿付けが簡単になるメリットがある一方、特別控除額が10万円まで減ってしまうのがデメリットです。
自分には白色申告と青色申告のどちらが向いている?
会社員が副業をする場合、白色・青色のどちらの申告方法が向いているのでしょうか。
- 白色申告が向いている人
- 青色申告が向いている人
白色申告は控除額こそ少ないものの、帳簿付けが簡単で事前の手続きもいりません。
副業収入が月換算で1万~2万に満たない場合は、白色申告でもさほど問題ないといえるでしょう。
副業収入が基礎控除の48万円(月4万)を超える場合は、青色申告を検討するのがおすすめです。
青色申告なら最大113万円までの控除が受けられますし、赤字の繰り越しなどの特典もあります。
ただし青色申告の利用には開業届の提出が必須です。また帳簿付けも複雑になるため、デメリットも含めて検討しましょう。
会社員の場合は本業と副業で忙しいため、事務処理が煩雑になると大変です。
そのため、副業を始めたてで収入が少ないうちは白色申告で処理し、副業が軌道に乗って収入が増えたら青色申告に切り替える方法もあります。自分にとってどちらがベストなのか、考えてみましょう。
会社員が副業をする際は、確定申告の要・不要を確認しておこう

会社員が副業をする場合は、確定申告が必要になる条件をしっかりと把握しておくことが重要。
確定申告が必要なのに申告をしなければ、重い追徴課税が課せられる場合もあります。「せっかく副業で収入を得たのに、追徴課税でそれ以上の税金を払わなくてはならなくなった」となれば本末転倒です。
また、副業収入によっては青色申告を選んだ方が節税できる場合もあります。
「会社員をしながら副業をスタートしてみたい」という方は、あらかじめ確定申告に関する知識をしっかりと身につけておきましょう。