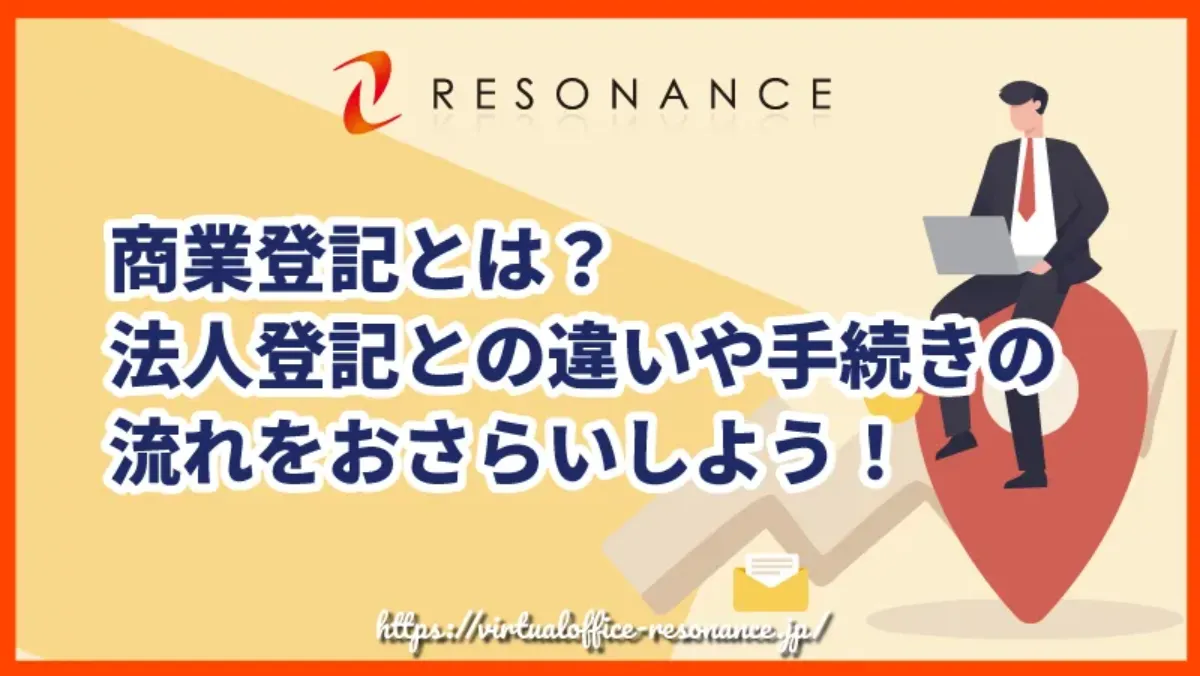企業経営者が新規事業や事業拡大に向けてまとまった資金を準備したい場合、金融機関から融資を受けるだけでなく「私募債」を活用する方法もあります。
中小企業やベンチャー企業にとって私募債は手軽な資金調達方法のひとつであり、私募債発行を通して企業のイメージアップを狙うことも可能です。
この記事では、私募債の概要や、私募債のメリット・デメリット、発行から償還までの流れについて解説します。
初めて私募債を発行する経営者は、ぜひ参考にしてください。
私募債とは?対象の異なる2つの種類について

企業が発行する社債は、公募債と私募債に分かれます。
公募債は、不特定多数の投資家を募集対象者とする社債です。
募集・発行手続きは複雑ですが、一度に多くの資金を調達できます。
一方、私募債は募集対象者を限定した社債であり、公募債と比べると法規制が少なく発行手続きもシンプルです。
私募債には調達規模が大きい「プロ私募債」と、より簡便に利用できる「少人数私募債」の2種類があります。
プロ私募債
プロ私募債の募集対象者は、金融機関に所属する機関投資家などの「適格機関投資家」のみとなります。
一方で、募集対象者数や発行総額は制限がありません。
プロ私募債発行企業の多くは、上場企業または中堅以上の非上場企業です。
プロ私募債を発行することで、証券保管振替機構のホームページで企業名を検索できるようになるため、知名度のアップにも有効です。
少人数私募債
少人数私募債は、募集対象者数が50人未満・発行総額が1億円未満・1口あたりの発行額が総額の1/50以上に制限されます。
プロ私募債とは異なり、プロの投資家だけでなく一般投資家に対する発行も可能です。
少人数私募債の場合は、発行者の親族・友人・取引先の縁故者などを募集対象とし、原則として担保・保証人は必要ありません。
ただし、社債を購入した人や社債購入の勧誘を受けた人などの「社債引受人」を50人未満に保つために譲渡制限が必要です。
私募債を発行するメリット
私募債には、公募債や金融機関からの借入にはないさまざまなメリットがあります。
そのため、中小企業やベンチャー企業などの経営者にとって試しやすい方法のひとつです。
新規事業立ち上げや事業拡大に伴いまとまった資金が必要になった場合は、私募債の発行を検討しましょう。
以下では、私募債を発行するメリットを紹介します。
低コストで手軽に発行できる
公募債を発行する際には、有価証券届出書や各種報告書が必要です。
有価証券届出書は司法書士や税理士などに依頼して作成してもらうため、手数料と手間がかかります。
一方で、私募債を発行する場合は有価証券届出書の提出が不要です。
また、金融機関から融資を受ける際に必要となる保証料も発生しません。
そのため、公募債や金融機関からの融資と比べて資金調達コストを安く抑えることができます。
保証人・担保の必要がない
少人数私募債は、発行者と引受人の信頼関係によって成り立つことから、融資などのように保証人を立てたり担保を用意したりする必要はありません。
そのため、保証人や担保が準備できず、融資を受けることができなかった人におすすめの資金調達方法です。
返済方式の柔軟性が高い
私募債は通常の融資と異なり、発行者が償還期限・償還方法・利率などに関する決定権を持っています。
例えば、償還期限は3~10年、利率は2~5%の範囲内で設定できます。
多くの引受人を募ってスムーズに取引を進めるためには、お互いに納得できる条件を設定することが大切です。
双方が安心して取引を行える
私募債は、会社法の規制に基づいて発行されます。
個人間でお金を貸し借りした場合、「いつまでに返すか」「利子はいくらか」などの取り決めが曖昧になり、トラブルに発展することが少なくありません。
一方で、私募債は規制に基づいた運用を行うため、お金にまつわるリスクを軽減できます。
発行者・引受人双方にとって、安心感の高い取引を行えます。
節税できる
発行者が引受人に対して支払った利子は企業の損金として扱えるため、節税につながります。
また、社債から生じた利子所得は分離課税となり、給与所得など他の所得と合算されません。
分離課税は超過累進税率の適用外となるため、利子を受け取った側の税負担も軽くすることが可能です。
私募債を発行するデメリット
公募債や銀行借入などに比べて手続きが簡単でメリットも多い私募債ですが、適切な準備をせずに発行を行った場合、損をする恐れがあります。
私募債発行を検討する際は、メリット・デメリットの両方を確認することが大切です。
以下では、私募債を発行する場合に考えられるデメリットを紹介します。
発行の審査基準が厳しい
保証機関を利用してプロ私募債を発行する場合、適債基準を満たしているかどうかを厳しく確認されます。
適債基準とは、企業の純資産額・自己資本比率・純資産倍率などに関する基準です。
適債基準を満たしていない企業は、私募債の発行が認められないため注意が必要です。
多くの手数料が必要となる
私募債を購入してもらうと、引受人に対して利子を払う義務が生じます。
銀行保証付私募債や信用保証協会保証付私募債を発行する場合は、財務代理人手数料・登録料・保証金なども追加で支払わなければなりません。
公募債の発行コストと比べると少ないものの、私募債の発行にまつわる出費がかさんだ場合は、一般的な融資よりも損をする恐れがあります。
償還時に一括返済しなければならない
私募債は満期一括償還が原則となっており、償還期限になると元金をすべて引受人に返済する必要があります。
また、私募債の償還期限は変更できません。
万が一、償還ができない場合は借り換えや増資などの検討が必要です。
ただし、借り換え・増資をした場合は、企業の信用が低下するだけでなく、融資の金利が上昇する可能性があります。
そのため私募債を利用する際は、資金繰りを綿密に考えたうえで発行することが大切です。
私募債の発行から償還までの流れ
以下は、少人数私募債発行から償還までの流れです。
①事業計画を立て、決議を受ける
社債発行の目的となる事業計画を立て、必要な資金額や償還期間を明らかにします。
募集要項・勧誘書類などを作成する際は、社内会議や株主総会での決議が必要です。
②社債引受人の決定・勧誘
社債引受人を決定し、説明会に参加してもらって勧誘を行います。
少人数私募債の場合、社債引受人の最大人数は最大49人までとなっています。
一度勧誘を行った場合、結果的に引き受けを希望しない人も引受人数に含まれるため注意してください。
③申込受付・審査
引き受けにあたって認識の相違がないかを最終確認するために、引受希望者に対して審査と申込手続きを実施します。
④発行金額の決定・募集決定通知書の作成
発行総額・引受人数・発行件数を確定し、口数・金額・振込口座を記載した募集決定通知書を引受人に送付します。
⑤申込金額の受領・社債券の発行
引受人に社債の購入金額を振り込んでもらって社債券を発行します。
各引受人に関する購入金額などの個人情報を社債原簿に記録しましょう。
⑥社債の償還
償還期間が終わったら、引受人に元金を償還します。
すべての社債を償還した時点で、私募債にまつわる工程はすべて終了です。
私募債による資金調達が向いている企業とは?

私募債の特徴について学んできましたが、自社に向いているのかが気になる方も多いのではないでしょうか?
私募債を使った資金調達が向いている企業は、以下の3つです。
- 小規模企業
- ベンチャー
- 合同会社などの持分会社
小規模企業
起業したての小規模な会社にとって、私募債は有効な資金調達方法だといえます。
特に少人数私募債であれば、資金調達をするうえでのコストや手間も少なく、担保・保証人を準備する必要もありません。
ベンチャー
ベンチャー企業では、資金調達方法のひとつとして私募債を活用する方法があります。
近年ではVC(ベンチャーキャピタル)やエンジェル投資家からの出資、クラウドファンディングなどを活用するベンチャーの割合が増えつつあります。もちろん、株式の発行や融資、補助金の利用といったベーシックな資金調達方法も健在です。
このような手法で資金調達を行っても、資金が不足する。または、本業が不調で新たな融資ができないといった場合の奥の手として「私募債の発行」を選ぶ企業が増えています。
合同会社などの持分会社
合同会社や合資会社、合名会社などの「持分会社」は、株式会社と同じ「会社」のひとつ。しかし、株式の発行や上場での資金調達はできません。
株式と異なり、私募債は会社形態にかかわらず発行が可能です。株式による資金調達ができない持分会社にとっては、有効な資金調達方法となり得るでしょう。
私募債を活用する方法とは?

発行が比較的かんたんな私募債ですが、実際の企業はどんな用途に私募債を活用しているのでしょうか。
- 新製品の開発資金として
- 事業進出資金の調達方法として
- 運転資金の確保に
私募債を自社発行することで、金融機関に頼らない資金調達ができます。とりわけ、少人数私募債ならば、少人数が対象にはなるものの、1億円までの資金を集めることができるのです。これを利用し、新商品・サービスの開発資金に充てたり、新規事業の進出資金として活用したりする企業が多く見られます。
新たな商品や事業を生み出す場合、成果が出ない限りは売上も発生しません。まずは私募債で先行投資し、より確実性・成功性の高いビジネスを生み出そうという考えが生まれるのは自然なことだといえるでしょう。
また、小規模企業や起業して間もない会社の「運転資金」として、私募債を活用するケースも多いです。私募債は償還日に一括で元金の支払いが必要にはなるものの、毎月の返済が不要です。これによりキャッシュフローが安定しやすく、事業へと注力しやすくなる効果が期待できるでしょう。
まとめ
公募債よりも簡単かつ低コストで発行できる私募債は、適格機関投資家を対象とするプロ私募債と縁故者を対象とする少人数私募債に分かれます。
効率よく資金調達するためには、企業の財政状況や調達したい金額に合った方法を選ぶことが重要です。
また、企業の財政状況が良好に保たれていなければ私募債の発行は認められません。
そのため、私募債を発行している企業は金融機関や投資家から優良企業と判断されるでしょう。
ここまで紹介したことを参考に、私募債発行を通じて事業の発展につなげましょう。